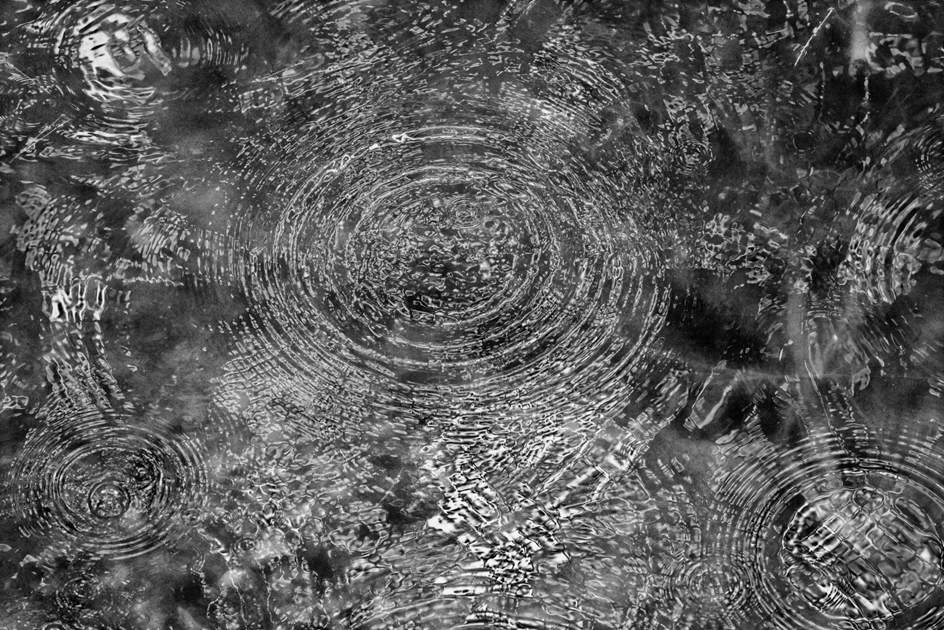
自然を表す言葉はない
ヘアート・ムル
(翻訳:藪本 雄登)
1万の日本の自然概念
本エッセイは、2024年から2025年にかけて日本で行われたクリエイティブ・リサーチ・レジデンシーを契機にまとめられたものである。このレジデンシーは、独自の自然観を持つ日本の自然学者、民族学者、民俗学者である南方熊楠(1867–1941)に関連しており、南方が生活し活動した古くからの巡礼路・熊野古道のふもとに位置する和歌山県紀伊田辺市で開催された。現在、同地には南方熊楠の博物館と資料館が所在する。
自然という言葉はない
山、木、動物、空気、水があるところには「自然」があると考えがちである。しかし、1890年以前の日本には「自然」という概念は存在しなかった。日本の風景、山や植物、動物、太古の森、海、空は、別の現実、別の経験、別の存在論、別の関係性ネットワーク、要するに、西洋の「自然」という言葉で捉えられるものとは異なるものであった。したがって、日本には「自然」を表す言葉は存在しなかった。
代わりに、文化的・精神的知識体系に基づいた、自然概念の多様で豊かな表現が深く根付いていた。これらの視点では、自然は人間、文化、環境の相互関係からなる、生きたネットワークとして存在し、美、詩、倫理、美学、人々、儀式、神々、季節と収穫、現れと消えゆくものなどが、一つのダイナミックな全体を構成する動的な自然現実を形成している。
西洋の自然概念が日本に根付いたのは1870年以降である。このときから、自然(shizen:自発的)という言葉は、西洋的な意味での「自然」を指すようになる。「自然」に「界」(特定の領域、境界、区分)が加わることで「自然界」という用語が生まれ、新たな自然の定義が明示された。これにより、新たな存在論も導入された。それは、自然は領域として、人間はそれに対置される主体として位置付けるものであった。
この西洋的な自然観は、日本において外来種のように広がり、地域的、多角的、相互的、文化的、社会的、精神的、美学的自然観に取って代わった。
この自然概念は、明治政府(1868–1912)によって採用され、それに付随する存在論とともに、政権の民族主義、植民地主義的、そして産業的な巨大プロジェクト、すなわち、「明治国家の建設」を可能にした思想的・技術的発展の重要な前提条件となった。そしてこの「明治国家の建設」は、近代日本史上最大の生態系破壊をもたらした。
日本初環境活動家であり、伝説的な自然学者兼博学者、そして日本最初の偉大な生物学者の一人である南方熊楠(1867–1941)は、自然に関する多数の著作や出版物を残したが、意識的に「自然」という近代化された用語を使用しなかった。その代わりに、人間、文化、自然を一つの生きた関係性のネットワークに織り交ぜられた構成要素として捉える、自然に関する概念を豊かに表現する多様な用語を用いた。
日本の自然概念の圧倒的な豊かさは、文化、仏教、神道の知識体系に根ざしており、独自の自然の法則を持つ平行宇宙への窓を開く。それは、支配的で行き詰まりをきたした産業資本主義と二元論的な生態学に代わる案を提示し、探求され、さらに形作られるのを待ち望んでいる。
1万の日本の自然概念(一部抜粋)
宇宙的自然
• 天地 (tenchi) – 天と地
宇宙の全体性を表す宇宙的二元性。神道儀式言語、古典文学、詩歌で頻繁に用いられる。
• 万物 (banbutsu) – すべての物 / すべての現象
存在するすべてのものを包括する包括的な概念 — 人間、動物、植物、霊的な存在を含む。
• 森羅万象 (shinra banshō) – 宇宙のすべての事物
仏教用語で、宇宙において生起し消滅するすべての現象を指す。
• 天地万物 (tenchi banbutsu) – 天地と万物
中国の思想における古典的な表現で、存在の全体を指す。
• 乾坤 (kenkon) – 統一体としての天地
儒教と道教における天と地が調和した一つの全体を意味する概念。哲学的なテキストや詩歌でよく用いられる。
• 陰陽 (in’yō) – 陰と陽
宇宙の原理として、互いに補完し合う対立物、動的な均衡、および循環的な変容を意味する。
• 自然 (jinen) – 「自ずからそうである」/ 自発的な秩序
中国語の「zìrán (自然)」に由来。これは世界の自然な、強制されない展開を意味する。現代日本語(1870年以降)では、文化と区別された物理的世界、および科学的研究の対象として用いられる。
• 天然 (tennen) –天与 / 先天的な
天や自然から与えられた自発的または内在的な状態。
• 天地四方 (tenchi shihō) – 天と地、東西南北の四方
古典的な宇宙論における表現で、空間の全体性を指す。
• 日月 (nichigetsu) – 日と月
光、時間、自然の周期を象徴する対の概念。
• 六合 (rikugō) – 六方
北、南、東、西、上、下の六つの方向を含む宇宙的概念。宇宙の全体を意味する。
• 天地四時 (tenchi shi-i-ji) – 天地と四季
宇宙の秩序と時間の流れを結びつけた古典的な概念。
美学的かつ詩的な性質
• 星辰 (seishin) – 星と天体
夜空とその天体を指す詩的な表現。
- 山河 (sanga) – 山と川
- 「山川」の文学的変形表現で、中国詩歌や古典散文に頻繁に見られる。
• 乾坤一擲 (kenkon itteki) – 天地を賭けて一投する
運命の瞬間や決定的な行動に全てを賭けることを比喩的に表現する。
• 風花雪月 (fūka setsugetsu) – 風、花、雪、月
自然の要素を詩的に列挙し、その美しさを讃える表現。
• 山川 (sansen / yamakawa[MOU1] [MOU2] ) – 山と川
特に和歌や俳句で用いられる風景の美を表現する用語。
• 万物 (banbutsu) – 万物 / すべての現象
中国哲学における包括的な用語で、人間、動物、植物、霊など、存在するすべてのものを指す。
• 風物 (fūbutsu) – 風と季節の物
特定の場所や時期に特有の、季節的な自然現象や文化現象を指す。俳句や季節暦において重要な概念である。
• 風月 (fugetsu) – 風と月
禅の美学と関連付けられる、はかない美の比喩。
• 花鳥風月 (kachō fūgetsu) – 花、鳥、風、月
自然の美しさを四季を通じて楽しむ詩的表現。
• 山水 (sansui) – 山と水
東アジアの美術や詩歌において、風景の要素の調和を表現する概念。山水画(sansui-ga)や庭園設計の主要なテーマ。
• 山海 (sankai) – 山と海
地域の地理的豊かさや広大さを表現する言葉。
• 四季 (shiki) – 四季
詩、絵画、儀式において自然を体験し表現する構造原理。
• 造化の妙 (zōka no myō) – 創造の妙
自然の創造力に内在する神秘的で崇高な美と調和を指す。
• 千変万化 (senpen banka) – 千変万化
自然や現象の無限の多様性と絶え間ない変容を表現する慣用句。
• 天地開闢 (tenchi kaibyaku) – 天地の明け始め
日本の創造神話において、宇宙が原始の混沌から誕生する場面。
• 四海 (shikai) – 四海
世界全体を象徴する表現。
• 日月星辰 (jitsugatsu seishin) – 太陽、月、星辰
天体のすべてを包括する詩的な表現。
• 春花秋月 (shunka shūgetsu) – 春の花と秋の月
季節の美しさを対比させ、対照と調和を表現する表現。
• 山紫水明 (sanshi suimei) – 紫色に染まった山々と清らかな水
極めて美しい風景の描写。
• 四時風光 (shiji fūkō) – 四季の光と風景
季節の移り変わりと共に変化する光と風景の詩的な表現。
• 秋風落葉 (shūfū rakuyō) – 秋風と落ち葉
季節の風景で、無常と衰えを象徴する。
• 春霞 (harugasumi) – 春の霞
早春の柔らかく霧のような光を表現する詩的なモチーフ。
• 朝露 (asatsuyu) – 朝の露
はかない美しさと人生の短さを比喩する。
• 花吹雪 (hanafubuki) – 花の吹雪
花びらが雪片のように舞い散る様子。
• 物の哀れ (mono no aware) – 物の哀れ
すべてのものの無常さを悟り、優しい悲しみを帯びた感情。
• 幽玄 (yūgen) – 神秘的で深遠な美しさ
自然や芸術に宿る、繊細で言葉に尽くせない優雅さを重んじる美学。
• 風流 (fūryū) ― 風と流れ
自然、季節、詩、芸術、舞踊、儀式などに調和した、洗練され育まれた感性。
• 侘寂 (wabi-sabi) – 簡素さと無常
不完全さ、はかなさ、素朴な美しさへの美的鑑賞。
• 寂 (jaku) – 内面の静けさ
禅の美学における静寂、不動、そして穏やかな存在感。
• 清明 (seimei) – 透明さと清らかさ
自然の清らかで輝く状態。また伝統的な春の祭り。
• 花鳥 (kachō) – 花と鳥
はかない自然の美しさを象徴する詩的な組み合わせ。
• 風姿 (fūshi) – 自然な物腰や姿
自然で調和の取れた形や態度。
• 花鳥虫魚 (kachō chūgyo) – 花、鳥、虫、魚
生き物の多様性を讃える古典的な列挙。
• 春花秋月 (shunka shūgetsu) – 春の花と秋の月
季節の美の対比で、調和と均衡を表現する。
• 山紫水明 (sanshi suimei) – 紫色に染まった山々と清らかな水
非常に優美な風景を表現した言葉。
• 四時折々 (shiji oriori) – それぞれの季節の移り変わり
季節の移り変わりに対する感性を表現した古典的な表現。
自発的秩序または存在の状態
• 自在 (jizai) – 自由自在 / 自然のまま
強制されない、本来の存在する状態。制約なしに行動したり存在したりする能力。
• 本性 (honshō) – 真の性質
人または物の本質的な性質や根本的な性格。
• 天工 (tenkō) – 天の技
儒教の思想において、宇宙の秩序と調和した自然の創造的な芸術性。
• 天運 (ten’un) – 天命
天の意志や宇宙の秩序に従って展開される出来事。
• 天地万象 (tenchi banshō) – 天、地、万象
存在するすべてのものの総体を表す別の表現。
• 自然 (jinen) – 自らある / 「自ずからそうである」
仏教・道教における、人為的でない、自発的な存在の形態としての自然の概念。
• 大自然 (daishizen) – 大自然 / すべてを包み込む自然
宇宙論的な概念で、広大で包摂的な総体を指す。
• 無為自然 (mui shizen) – 無為と自然らしさ
道教の核心的な原理で、自然の道に調和した努力を要しない行動を指す。
• 天地自然 (tenchi shizen) – 天地と自発的な秩序
宇宙の二極性と自然の自己秩序原理の統合。
• 造化 (zōka) – 自然の創造力
道教と仏教の用語で、自然界の生成と変容の力を指す。
• 天真 (tenshin) – 天の真心 / 自然の純粋さ
無垢で飾らない、真実と純粋さの状態。
• 天理 (tenri) – 天の法 / 自然の法
普遍的な道徳的または宇宙的な秩序。
• 自然法爾 (jinen hōni) – 「自ずからそうである、あるべき姿
親鸞の浄土真宗の仏教用語で、現実が真の本質に従って自然に展開する状態を表す。
生命力と内なる本質
• 命 (inochi) – 生命
存在の根本的な本質と精神的な本質。
• 精神 (seishin) – 心 / 精神 / 魂
物質を超えた生命力と意識、そして存在の精神的・霊的な次元。
• 生命 (seimei) – 生命 / 生命力
生物学的生命と精神的活力の両方を包含する概念。
• 血脈 (ketsumyaku) – 血統 / 生命の源
活力、血統、継承の象徴。
• 活力 (katsuryoku) – 活気/ 生命エネルギー
活発な身体的・精神的エネルギー。
• 気 (ki) – 生命力
すべての生き物に遍在する普遍的な呼吸、あるいは生命力。東アジア思想の中心。
• 性 (sei) – 存在 / 本質
存在や物の本質的な特性や先天的な性質。
• 元気 (genki) – 原初のエネルギー / 生命力
生命を維持する生命力。現代日本語では健康、活力、または明るさを意味する。
• 根源 (kongen) – 起源 / 源
すべてのものが生じる根本的な起源。
• 草木 (sōmoku) – 草と木
植物界の総称。
• 山野 (sanya) – 山と原野
未開地または半野生の風景と移行地域。
• 精気 (seiki) – 生命の精気 / 生命の精髄
生き物の生命を動かす霊的なエネルギー。
• 呼吸 (kokyū) – 呼吸 / 呼吸作用
生命とエネルギーの源。禅や武道では、集中とバランスを養う実践。
• 栄養 (eiyō) – 栄養 / 栄養素
生命の維持と成長の源。
• 循環 (junkan) – 流れ / サイクル
エネルギー、物質、または季節の循環的な動き。
• 脈動 (myakudō) – 脈動 / 拍動
生命と自然のリズム的な鼓動。
社会文化的性質
• 入会林 / 入会地 (iriai-rin / iriai-chi) – 共同利用林 / 共同利用地
伝統的な村落が管理する木材、葦葺き材、狩猟動物、その他の共有資源の採集を目的とした山林および原野。
• 里山 (satoyama) – 村山地域
集落と山地の間に位置する半自然的な文化景観で、農地、森林、自然が調和して管理されている地域。
• 月見 (tsukimi) – 月を愛でる
秋の満月を鑑賞するための人々が集まる季節の風習。
• 花見 (hanami) – 花盛りを愛でる
春に咲き誇る桜の木の下で地域の人々が集まる祭り。
• 雪見 (yukimi) – 雪を愛でる
雪に覆われた庭や風景を楽しむ冬の風習。
• 里海 (satoumi) – 里と海
漁民によって管理される沿岸地域で、海洋資源と海岸線の持続可能な利用が行われている区域。
• 裏山 (urayama) – 村の裏手にある山
集落の背後に位置する森林地帯で、日常的な資源利用に用いられ、しばしば儀式的な意義を持ち、通常は村落の管理下にある。
• 入浜権 (irihama-ken) – 干潮帯採集権
潮間帯における海藻、貝類、その他の海洋資源を採集する伝統的な共同利用権。
• 山野 (sanya) – 共同の山と野原
藁葺き材、薪、野草の採集地で、村民間で共有されることが多い。
• 野良 (nora) – 未開墾地
共同利用される開けた草原や農地。
• 村山 (murayama) – 村と山
木材、狩猟、その他の資源の管理のために共同で管理される森林や山地。
• 漁場 (gyoba) – 水産物を得る場所
漁業共同体によって共同で利用される海や川の水域。
• 御林 (ohayashi) – 保護林
地方自治体、寺院、神社が所有または管理し、保護区域として指定された森林。
• 保安林 (hoanrin) – 法的に保護された森林
浸食、洪水、その他の環境災害から保護するために指定された森林。
神聖的性質
• 神山 (kamiyama) – 神聖な山
神々が住むとされている山。
• 神海 (kamiumi) – 神聖な海
神話的または宗教的な意義を持つ水域。
• 神泉 (shinsen) – 神聖な泉
神聖な特性を持つ自然の水源。
• 龍神 (ryūjin) – 龍の神
水、海、雨を司る神話上の守護神。
• 神風 (kamikaze) – 神の風
歴史的・精神的な神聖な保護の象徴。
• 鎮守の森 (chinju no mori) – 神聖な神社森
神社の周囲を囲む林で、儀式と生態系の両方の機能を果たす。
• 御神木 (goshinboku) – 神聖な木
神(kami)の霊が宿ると信じられる木。
• 神域 (shin’iki) – 神聖な自然区域
神社や寺院の周囲に設けられた保護区域で、生態系が保存されていることが多い。
• 八百万の神 (yaoyorozu no kami) – 極めて多くの神々
自然界に存在し、それを支える無数の神々を指す言葉。
• 山の神 (yama no kami) – 山の神
山、農業、狩猟、季節の巡りを見守る守護神。
• 田の神 (ta no kami) – 田んぼの神
収穫と豊穣の守護神。
• 磐座 (iwakura) – 神聖な岩
神が座する自然の石の形成物。
• 御神水 (goshinsui) – 神聖な水
儀式や霊的な意味を持つ泉や川の水。
• 神木林(shinboku-bayashi) – 神聖な林
神社を囲む神聖な立木。
• 八百万神境 (yaoyorozu shinkyō) –無数の神々の世界
数多くの神々が住む自然の神秘的な次元。
• 霊界 (reikai) – 霊の世界・精神世界
霊魂、先祖、神々が存在する目に見えない世界。
• 神楽 (kagura) – 神聖な舞踊と音楽
神を祀る神道の儀式的な舞踊と音楽。季節の祭りと結びついていることが多い。
• 雨乞い (amagoi) – 祈雨
干ばつの際に雨を降らせるための儀式。
• 火祭り (hi matsuri) – 火の祭り
火を使った清めの儀式。
• 水祭り (mizu matsuri) – 水の祭り
水神を祀る儀式。
• 湯垢離 (yu-gori) – 温泉での清め
神社や寺院を訪れる前に清めるための儀式的な入浴。
• 護摩焚き (goma taki) – 火供の儀式
修験道と密教の儀式で、守護、願い、清めの目的で行われる。
• 甑岩 (Koshikiiwa) – 蒸籠岩
地元の神を祀る自然の岩の聖地。
• 熊野権現 (Kumano Gongen) – 熊野権現
神聖な自然の場所における神道と仏教の神々が融合した神々の現れ。
• 御神体 (goshintai) – 神の聖なる身体
神が宿るとされる自然物(岩、木、山、滝など)。
• 社叢 (shasō) – 神社の森
神社を囲む古木立で、生態系の保護区域と儀式空間の両方の役割を果たす。
• 結界 (kekkai) – 神聖な境界
神聖な場所を保護するために儀式的に区画された区域。
• 遥拝所 (yōhaisho) – 遠隔礼拝所
神聖な山や岩を遠方から拝むための展望地。
• 水神 (suijin) – 水の神
泉、川、灌漑システムなどに宿る地域の水霊。
• 木霊 (kodama) – 樹霊 / 反響
木々を生命体として崇める信仰。森に響く音は精霊の存在を示すものとされる。
• 天狗 (tengu) – 山と風の神
山岳の頂上や原始の森を守ると伝承される伝説上の守護神兼いたずら者。
• 河童 (kappa) – 水の精霊
民話に登場する川や池の生物で、灌漑や水安全と関連付けられる。
• 岩屋 / 岩窟 (iwaya / gankutsu) – 神聖な洞窟
神や仏の住処として機能する洞窟。風景における境界的な門戸。
• 霊峰 (reihō) – 神聖な峰
宗教的な意義を持ち、巡礼の伝統がある山。
• 磐境 (iwasaka[MOU3] ) – 神聖な岩の囲い[MOU4] [MOU5]
儀式や神聖的な重要性を持つ、石で囲まれた特定の区域。
• 霊水 (reisui) – 神聖な水
霊的なエネルギーが宿った泉や川の水。
• 神籬 (himorogi) – 仮設の神棚
常緑の枝で囲まれた、神が降臨する場所。
• 依代 (yorishiro) – 神霊の宿る物/ 神を招く物
神霊を招き寄せたり宿らせたりする物体や場所。
• 神饌 (shinsen) – 神への供物
神道儀式や祭礼で供えられる食物や飲料。
• 祭礼 (さいれい) – 季節の儀式または祭り
人間と自然の調和を育む祭典。
• 盆踊り (bon odori) – 盆踊り
先祖の霊を祀る夏の儀式舞踊。
• 花祭り (hana matsuri) – 花祭り
仏陀の誕生を祝う春の祭り。
• 豊年祭 (hōnen-sai) – 収穫祭
豊作を祈願する祭りと行事。
• 星祭り (hoshi matsuri) – 星祭り
天体を祀る儀式。
• 風祭り (kaza matsuri) – 風祭り
良い風と守護の風を祈る祭り。
• 御田植祭 (otaue matsuri) – 稲植えの神事
農業作業と季節のサイクル、神聖なサイクルを結びつける儀式。
• 山開き (yama biraki) – 山開きの儀式
登山や巡礼のシーズンの始まりを告げる儀式。
• 海開き(umi biraki) – 海開きの儀式
漁業や水泳のシーズンの始まりを告げる儀式で、海神への供物を捧げる。
• 節分 (setsubun) – 季節の分かれ目の儀式
悪霊を追い払う祭り。豆を撒く習慣がある。
• 注連縄 / 七五三縄 (shimenawa) – 神聖な稲わら縄
神聖な存在を象徴し、神聖な領域と俗世を区切る。
• 紙垂 / 四手 (shide) – ギザギザの紙の帯
注連縄や枝に付けられ、清浄と神聖な存在の象徴として用いられる。
地域的・民間の性質
• 熊野古道 (Kumano Kodō) – 熊野巡礼ルート
和歌山県の熊野地方に広がる、聖なる森、川、滝を結ぶ古代の山道ネットワーク。
• 那智の滝 (Nachi no Taki) – 那智の滝
神聖な滝であり、崇拝の場所。水は生きている清浄な力として崇められる。
和歌山県熊野に位置する。
琉球の自然 – 沖縄と周辺諸島の先住民族の概念
• 御嶽(ウタキ) – 神聖な森や岩の聖地
自然の聖域として機能する宗教的中心地で、伝統的に巫女によって管理されてきた。
• カミアサギ (kami asagi) – 神の あずまや
儀式やコミュニティの集まりに用いられる開放的な儀式堂で、通常は御嶽(ウタキ)内またはその隣接地に位置する。
• 浜下り (hamaui) – 潮水清め儀式
季節ごとの海水での清め儀式で、伝統的に女性と子供によって行われる。
• シヌグ (shinugu) – 山の夏行事
踊りや歌、供物を捧げる祭りで、コミュニティの保護と豊作を祈願する。
• ノロ (noro) – 女祭司
コミュニティと霊的な自然界の仲介役を務める女性の神職、祭司。
• ニライカナイ (Nirai Kanai) – 遥かな海の地平線(理想郷) / 祖先の地
地平線の彼方に存在する生命と豊穣の神話的な源。
• 竜宮 (Ryūgū) – 海底の竜宮
潮の満ち引きと生命のサイクルと象徴的に結びついた海洋の異世界。
アイヌの自然 – 北日本先住民族の概念。
• カムイ (kamuy) – 霊的な存在 / 神々
動物、植物、風景、自然の力などに宿るアニミズム的な霊魂で、人間と相互関係にある。
• アイヌモシリ (Ainu Mosir) – 人々の土地
人間と自然が共存する世界。
• カムイモシリ (Kamuy Mosir) – 神々の地
目に見えない霊的な世界と目に見える自然世界とが結びついた領域。
• イナウ (inau) – 儀式用の供物棒
カムイへの供物として、川や森の縁、狩場などに置かれる彫刻された柳の棒。
• ヌサ (nusa) – 屋外祈祷用祭壇
自然の中の聖なる場所で、カムイへの供物として木製の祈祷棒が立てられることが多い。
• カムイチェプ (kamuy chep) – 神聖な魚(サケ)
季節の儀式の中核を成し、主要な食料源の一つ。
• シントコ (shintoko) – 神に酒を供えるための神聖な漆器
儀式的な清めや祈祷に用いられる。
• イオマンテ (iomante) – 熊送りの儀式
熊の神の霊を神界に戻す儀式で、森の道徳規範を尊ぶ。
• カムイ (kamuy) – 自然の霊的力
自然現象、動物、風景に宿る神聖な力。
現代の自然(1890年以降)
• 自然 (shizen) – 自然
1870年以前:中国仏教の「自然」(zìrán)から由来し、「自らそうである」という意味の宇宙的原理。人間から独立した物理的対象ではなく、自発的な秩序の原理。
1870年以降:西洋の客観的な自然観の翻訳として再定義され、文化と対立する物理的領域であり、科学の対象となる。
• 大自然 (daishizen) – 大自然
1870年以前:近代以前の文献では、固定用語としてはあまり見られない。
1870年以降:現代の自然概念の拡大された宇宙論的解釈で、科学的または民族主義的ロマン主義的文脈でよく用いられる。
• 自然界 (shizen-kai) – 自然界
新語:科学的な新語。「界(kai、領域)」は明治期以降、生物学、地質学、生態学において、体系的に適用された。
• 生物界 (seibutsu-kai) – 生物界
新用法:「有機界」や「生物界」といった西洋用語の翻訳としての造語。「生物」自体は明治時代の「有機体」を意味する造語で、1870年以前の相当語はない。
• 動植物 (dōshokubutsu) – 動物と植物
1870年以前:動物と植物は別々に呼ばれていた(例:鳥獣と草木)。単一の二元的な科学的分類はなかった。
1870年以降:動物界と植物界を統合する科学的分類用語。
• 元気 (genki) – 活力 / 精力
1870年以前:中国医学や宇宙論における生命力や活力の哲学的・医学的用語(気/ki)。
1870年以降:物理学や生物学においても「エネルギー」や「物理的力」を意味する用語として、西洋のモデルに倣って使用されるようになった。
• 天然 (tennen) – 自然
1870年以前:「天から与えられた」または「先天的な」。
1870年以降:西洋の自然/文化二元論の影響を受け、「人工的でない」という意味に拡張された(例:天然資源 、自然資源)。
• 無為自然 (mui shizen) –作為がなく自然のまま
1870年以前:道教の 無為 と自発的秩序の原則。
1870年以降:西洋の影響を受けた生態学や社会哲学の文脈では「自然のバランス」と再解釈されることがある。
• 本然 (honzen) – 本来の性質
1870年以前:儒教の哲学用語で「本来の状態で」「内在する性質」を意味する。
1870年以降:心理学、生物学、法学において「後天的なもの」の対義語として使用される。
• 生命力 (seimeiryoku) – 生命力 / 生命エネルギー
新用法:西洋の」生命力」概念に影響を受けた科学的・生物学用語。
• 科学的自然観 (kagakuteki shizenkan) – 科学的自然観
新用法:「scientific」(科学的)の翻訳として導入された「科学的」と「自然観」の複合語。
• 環境 (kankyō) – 環境 / 周囲
1870年以前: 稀に用いられ、文学的・哲学的文脈で」周囲の条件」を意味していた。
1870年以降:自然科学や環境科学において「environment」(環境)の翻訳語として定着。
• 自然環境 (shizen kankyō) – 自然環境
新用法:生態系や景観を指す科学用語で、地理学、生態学、環境保護の分野で広く用いられる。
• 自然科学 (shizen kagaku) – 自然科学
新用法:物理学、化学、生物学などの経験科学の総称。
• 生態学 (seitaigaku) – エコロジー
新用法:20世紀初頭にドイツ語の「Ökologie」から借用。生態(「生きている状態/形態」)と学(「研究、科学」)から成る。
• 生態系 (seitaikei) – エコシステム
新用法:第二次世界大戦後に「ecosystem」(エコシステム)の翻訳として導入された。
• 自然保護 (shizen hogo) – 自然保護
新用法:20世紀初頭から使用される政治的・法的用語で、特に国立公園の文脈で用いられる。
• 国立公園 (kokuritsu kōen) – 国立公園
新用法:1930年代に導入され、西洋の例を模倣した用語。
• 天然記念物 (tennen kinenbutsu) – 天然記念物
新用法:保護対象の種や景観を分類する法的カテゴリー(1919年から)。
• 地球 (chikyū) – 地球(惑星)
1870年以前:宇宙論や仏教文献において、世界体系内の」地面」または「円盤状の地球」(地球平面説)を指す。
1870年以降:現代の天文学と地球科学において「earth」(地球)の標準的な翻訳として定着。
• 地球環境 (chikyū kankyō) – 地球環境
新用法:20世紀後半から一般的になり、気候変動や国際環境政策の文脈で使用される。
• 自然災害 (shizen saigai) – 自然災害
新用法:現代の行政、災害管理、気象学における用語。
• 自然選択 (shizen sentaku) – 自然選択
新用法:ダーウィンの進化論における「natural selection」の直訳。
• 進化論 (shinkaron) – 進化論
新用法:ダーウィンの進化論を含む後の進化論を指す用語。
• 生物多様性 (seibutsu tayōsei) – 生物多様性
新用法:1990年代以降広く使用されている」biodiversity」の現代的な翻訳。
• 環境倫理 (kankyō rinri) – 環境倫理
新用法:20世紀後半に生まれた哲学的・政策用語で、西洋の環境思想に強く影響を受けている。

へアート・ムル(Geert Mul)
2025年8月
2024年から2025年にかけて日本でのアーティスト・イン・レジデンス期間中、私は南方熊楠(1867–1941)の生涯と業績を研究した。南方は先見の明を持つ思想家、環境活動家であり、日本初の偉大な生物学者の一人である。彼は、仏教と神道の自然観を多分野・学際的な科学研究と融合させ、多様性、逸脱、変容、多元性が中心となる自然と文明の新たな世界観を築いた。
このビジョンは、現代においてますますその重要性を増している。このレジデンシーは オランダ王国日本大使館、オランダ創造産業基金、および日本・紀南アートウィーク支援・主催により開催された。ここに、藪本雄登氏(紀南アートウィーク)と四方幸子氏のご支援に心より感謝申し上げたい。
また、写真と制作を担当した下田学氏、および南方熊楠に関するご意見を共有いただいた唐澤 太輔氏にも深く感謝申し上げたい。
[MOU2]読みはyamakawa?
[MOU4]https://nippon-bunmei.jp/amanoiwakura-t4.htm
