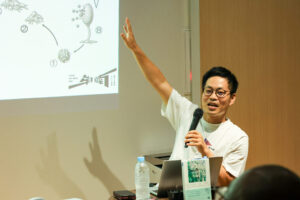コラム

「ややこしさ」の系譜 ―おくゆかしき青姦性を求めて—
紀南アートウィーク実行委員会
藪本 雄登
写真:下田学
「ややこしき いざなみ」
熊野三山を巡る一連のリサーチトリップを終えて、私の中に残ったのは、ある明確な違和感だった。それは、この土地の自然が持つ圧倒的な「単純さ」と、私たち人間が生きる世界の「複雑さ」との間に横たわる、埋めがたい落差である 。

潮岬の森林群:美しい空と森のかたち
自然の「率直さ」という衝撃
熊野・那智の滝の前に立ったとき、まず感じたのはその「率直さ」だった。滝はただ、落ちている。そこにはためらいもなければ、経験の蓄積による澱みもない。重力に従い、水は落ち、砕け、霧となり、再び循環の輪へと戻っていく。そこにあるのは純粋な運動そのものであり、それ以上でもそれ以下でもない。意味は、後から人間が勝手に付与するものであって、滝そのものは自己を説明するための意味を必要としていない。

那智の滝を望む参加メンバーたち
神倉神社の岩倉(ゴトビキ岩)に立ったときも、私は同じ感覚を覚えた。露出した巨石は、ただそこに「ある」。それだけで完結している。何千、何万という年月を経てそこに存在しているはずなのに、そこには「時間の蓄積」という重苦しさはなく、むしろ「時間の不在」とでも呼ぶべき軽やかさが漂っていた。

鬼ヶ城で座り込むアーティストの石田真也

ゴトビキ岩にふれるアーティストの大小島真木

神倉神社の石段を降りるアーティストの坂本大三郎
花の窟神社の剥き出しの岩窟も同様である。そこは黄泉の国、つまり、「死」の神話と密接に結びつけられた場所だ。しかし、私がそこで感じたのは死の重苦しさではなく、むしろ開かれた空間の「軽さ」であった。岩は何も語らない。ただそこにある。その沈黙は、人間の語りを拒絶しているのではなく、そもそも必要としていないのかもしれない。

花の窟神社の剥き出しの岩とアーティスト大小島真木の息子 千花人

御百度石:新宮の大馬神社にて
「ややこしさ」という人間の発明
他方、人間はどうだろうか。人間は生きるために制度を設計し、関係を築き、あらゆる事象に意味を重ねる。その過程で、世界は次第に層をなし、重くなり、そして、「ややこしく」なる。つまり、「ややこしさ」とは、人間が生活を営む上で生み出した「生の副産物」なのではないか。それは生きた証明でもあるが、同時に、私たちの生を拘束する鎖でもある 。
私たちが紀南の重層的な歴史や、南方熊楠という巨人の足跡、あるいは、熊野古道の道を歩いたり、触れるとき、ついそこに「複雑怪奇な深淵」を見出そうとしてしまう。だが、実際に那智の滝を見上げ、花の窟の巨大な岩壁を仰ぎ見たとき、突きつけられるのは驚くほどの「シンプルさ」である。
そこにあるのは剥き出しの自然であり、圧倒的な質量を持った岩であり、垂直に落ちる水という事実だ。それらは極めて「からっ」としていて、清々しい。人間が後付けで付与する「湿り気を帯びた複雑さ」など、そこには微塵も存在しない。
ならば、私たちが日常で感じている、あのまとわりつくような「ややこしさ」の正体とは何か。それは、人間が日々の生活を積み重ねる中で、自らの苦しみの中から絞り出すようにして発明してきたものに他ならない。

潮岬の森で、祀られる岩を見つめるアーティストの渡辺志桜里
風土が生成する「ややこしさ」の温度差
その「ややこしさ」の質は、その土地の気候や時間の流れに規定される 。
例えば、昨年歩いた東北・遠野の地を想う。そこでは冬が長く、人々は分厚い雪の下で、じっと耐え忍ぶ時間を強いられる。生活の苦しみは慢性的な重みを持ち、時間は粘り気を帯びて流れる。そうした環境下で醸成される「ややこしさ」は、内省的で、しめやかで、どこか生々しい。それは死の気配が常に生活の隣に寄り添っているような、おくゆかしく、そして、重厚な死生観である。柳田國男が『遠野物語』で描き出した世界は、まさにこうした時間の堆積が生んだ精神構造とも言えるだろう。
一方、紀南はどうだろうか。ここは温暖な光に満ち、風はさっぱりと吹き抜ける。生死の天秤で言えば、圧倒的に「生」の要素が強い土地だ。南方熊楠という男が、タブーを恐れず「性」を前面に押し出したのは、この土地の持つ剥き出しの生命力に呼応した結果ではないか。熊楠が提示した生死観は、いささか語弊を恐れずに言えば「青姦的(かつ、早漏的)」ではないか。つまり、熊楠にとって、生と死は対立するものではなく、循環の異なる局面に過ぎなかった。彼にとって重要だったのは、持続する個体としての生命ではなく、生成と消滅が絶えず反復される高速運動そのものだった。

大馬神社で祀られる川と坂本大三郎
ここで注目すべきなのは、その運動が、制度的に保護された空間の内部ではなく、常に自然の只中で生起しているという点である。それは準備された舞台の上で慎重に展開されるものではなく、むしろ予告なく発生し、短く燃焼し、そして速やかに自然へと回収されていく。
つまり、それは内側で守られる生ではなく、外側に露出した生である。蓄積や持続によって保証される生ではなく、放出によって、瞬間的に現れ、消えては巡っていく生である。私は、この生の様態を表す比喩として、「青姦性」という言葉を用いたい。
ここで言う「青姦性」とは、単なる逸脱的な行為を意味しない。それは、制度や建築の内部に囲い込まれた生とは対照的に、自然の開かれた空間の中で、媒介なしに発生し、短く燃焼し、そして痕跡をほとんど残さずに消えていく、生の露出的な形式を指している。それは隠蔽ではなく露出であり、 持続ではなく「早漏的」な放出であり、 所有ではなく循環である。
紀南の青姦性とお燈祭り

お燈祭りで、瞬間的に一気に燃え上がる炎
この「青姦的」な生の様態は、「お燈祭り」に象徴されていた。数千人の男たちが松明を手に、急峻な石段を駆け下りる。男たちが、そそくさと現場に集い、点火と同時に爆発的なエネルギーを放出し、一気に「果てる」。その運動は、長期的に維持されるものではない。
それは極めて短い時間の中で、爆発的に燃焼し、そして終わる。この短さこそが重要なのである。
エネルギーは保持されるためではなく、放出されるために存在する。そして、放出された瞬間、それは個人の所有物ではなくなり、再び風土の中へと分散していく。この瞬間的で、野外的で、非蓄積的な生の形式――それこそが、この土地の持つ根源性ではないだろうか。
それは、理屈や複雑な手続きを飛び越えた、乱交的なまでの生死(精子)の循環だ。そこには、遠野のような「じっくりと死を見つめる」間尺はない。一瞬の生の爆発、そして巡っていく生と性。その潔いまでのシンプルさが、紀南の根底には流れている 。
柳田國男が、熊楠のこうした奔放な生(性)死観に嫌悪感を抱いたのは、当然のことかもしれない。柳田の求める「死」は、もっと儀礼的で、秩序だった「おくゆかしさ」の中にあったからだ。

一気に着火していく松明と男たち
「ハイブリディティ」の必要性とアーティストの役割
しかしながら、私たちは今、そのどちらか一方を選択するのではなく、両義性を抱え込む「ハイブリディティ」を必要としている 。
紀南の持つ、あのからっとした「青姦性」の中に、東北的な、あるいは人間が生活の中で生み出してきた「おくゆかしさ」をいかに接合していけるのだろうか。単なる野生への回帰ではなく、かといって人間中心的な複雑さに溺れるのでもない。いわば「おくゆかしき青姦性」という、一見矛盾するような質感をこの地に生み出すこと。そこにこそ、今、アーティストが介在する意味ではないか 。
今回のツアーにおいて、その象徴的な結節点となったのは、偶然、二日前に出会い、ひょんなことから参加してくれた大小島真木と、共に歩んだ辻陽介の存在であった 。
大小島が諏訪の地で向き合い、生み出し、そして、遠野でみた「千鹿頭(ちかと)」という映像作品 。それは、自然と人間、男と女、狩る者と狩られる者、神と獣が混ざり合う、まさにハイブリッドな象徴である。そして、今回のツアーの現場には、その名を授けられた大小島の息子「千花人(ちかと)」の姿があった。

アーティストの辻陽介と息子の千花人
驚くべきことに、まだ幼い彼は、あの凄まじい熱気に包まれたお燈祭りに参加していた。大人たちが松明を手に、我先にと石段を駆け下りる狂乱の渦。その爆発的な生のエネルギーの中に、千花人という小さな命が混ざり合っていたのだ。暑さの中で滴る熱気を感じながら、彼が見つめた景色はどのようなものだっただろうか。
母が諏訪の深い森から手繰り寄せた「千鹿頭」という神話が、息子の身体を通じて、紀南の剥き出しの「生」の現場と衝突し、溶け合っていく。そこには、土地から土地へと受け継がれる「生死のハイブリティ」が、理屈を超えた確かな手触りを持って存在していた。
未だ言葉にならぬ「かたち」の予兆
今回のツアーを共にしたアーティストの坂本大三郎と渡辺志桜里もまた、この地で何らかの強烈な「予兆」を受け取っていたはずだ。
山伏としての実践を通じ、自然と人間の境界線を歩き続ける坂本 。そして、国家/制度の在り方を冷徹かつ詩的な視座で解体しようとする渡辺。彼らが、あの那智の滝の飛沫の中で、あるいは熊野や鬼ヶ城の異形の岩肌を前にして、何をみて、何を感じたのか 。

熊野古道の地蔵に祈りを捧げる坂本大三郎
様々な対話がなされたが、今はまだ、それを安易な言葉に落とし込むべきではないだろう(まだ、落とし込みたくない)。彼らの中にある感覚は、今まさに紀南の温暖な湿気と、岩の無機質な感触の間で、発酵し始めているはずだ 。
紀南の自然は、どこまでもシンプルで、正直だ。「ややこしさ」は、人間がこの世界で生きていくために発明してしまった業のようなものだ。しかし、その「ややこしさ」を、紀南の圧倒的な「生」のエネルギーにぶつけるとき、そこには新しい「かたち」が生まれる。それは、早漏的に果てるだけの刹那的な生でもなく、雪に閉ざされた永劫の死でもない。激しく入り乱れ、ぐるぐると巡りながらも、どこか凛とした静けさを湛えた、新しい時代の神話である。
今回の熊野三山アートトリップは、その序章に過ぎない。アーティストたちが、この「シンプルで強靭な自然」に、いかなる「人間的ややこしさ」を編み込み、新たなハイブリディティを提示してくれるのか。
その「かたち」が現れる瞬間を、私は静かに、しかし昂揚感とともに待っている。紀南の岩たちは、今日も変わらず、ただそこに在る。その潔いまでの無言の圧力に、私たちは表現という名の「ややこしさ」を持って、精一杯の誠実さで抗い続けなければならないのだ。

熊野古道の木の中に入り込む渡辺志桜里(上)
熊野古道をゆっくりと歩く筆者たち(下)