みかんコレクティヴ

みかんコレクティヴの現座標 (中編)
–ヴェネチア・ビエンナーレとドクメンタを巡って–
紀南アートウィーク 藪本 雄登
1 はじめに -ルアンルパとイリイチ-
前編では、第59回ヴェネティア・ビエンナーレ(会期:2022年4月23日〜11月27日、以下「ビエンナーレ」)とドクメンタ15(会期:2022年6月18日〜9月25日、以下「ドクメンタ」)を実際に巡った上で、「脱人間中心主義」、「ダナ・ハラウェイの思想」、「再魔術化」等について述べたが、中編では、ドクメンタの内容を中心に、イヴァン・イリイチ(Ivan Illich、1926年-2002年)の「コンヴィヴィアリティ」を中心に述べる。



ドクメンタ開幕後、ArtReview[1]、The Art Newspaper[2]、Artforum[3]等において、今回の展覧会について、否定的な内容のレヴューが出されている。ただ、筆者の結論を述べると、良い意味で「目新しいものがなかった」というものだ。というのも、東南アジアで接してきたアーティストやコレクティヴの活動が、そのままカッセルという場所で行われていただけであり、オープニングの現場では、展示を見るというより、半ば同窓会のように、かつての友人などと、だらだらと食事を食べ、お酒を飲みながら、会話するといったものであった。また食事会、コンサート、ライブ、ナイトクラブ、カラオケ、サウナ(!!)等の充実したイベント・プログラムによって、展示よりもフェスに近い体験だったといえる。ある意味、「アートより友達(Make friends not art![4])」を標榜するルアンルパの思惑通りではあったのではないかと思う。


原子炉ではなく、元気炉。東日本大震災におけるメルトダウンは、歴史上最大規模の原発事故となった。これは科学的に文明化された社会に対する根深い不信を引き起こし、田中功起やチンポム等に代表される「芸術における社会的転回」における重要な動力の一つとして機能した経緯がある[5]。この文脈を踏まえ、福島第一原発を模した可動式サウナは、ドクメンタ開催中、場所問わず、展開可能となっている。カッセルで取れた薬草サウナで語り合った後、元気茶とドクメンタビールと交互に飲みながら、さらに見知らぬ他者を巻き込んでいく。そして、さっきサウナに入った人達が、元気炉で得た動力を得て、瞬間的に新しい他者を巻き込んでいった。
アーティストの栗林隆(Takashi Kuribayashi[6])氏の発言で印象的な言葉は、他者を「干渉しない」ということ。アジアのコレクティヴの活動には、ときに政府に対する対抗措置として、署名活動等の「連帯」が求められたそうだが、彼らは、それらに容易に応じない。彼らの活動は、誰にも干渉されないし(自律し)、干渉もしない(他律もしない)。彼らの実践からは、後述するコンヴィヴィアル(Convivial)な思想の一部が垣間見えたような気がした。
確かに、「アートより友達」という独り歩きしそうな言葉は、「芸術の社会的転回」を提示したクレア・ビショップ(Claire Bishop)が「敵対と関係性の美学」において、ニコラ・ブリオー(Nicolas Bourriaud)の「関係性の美学」を批判した(身内だけで排他的に集まり、単に調和的な関係を構築しているだけではないか、という批判)と同じような議論[7]を引き起こす可能性がある。なお、「芸術の社会的転回」、「関係性の美学」や「アートコレクティヴ」等については、過去実施した「農業×アートコレクティヴ -糸島芸農から学ぶ-」の江上賢一郎氏の整理を参照いただきたい。
また、「ヴァナキュラー(vernacular)」な場所で実践を行い、成果を上げるコレクティヴを、わざわざドクメンタにおいて見世物にする必要があるのか、ということも一つの批判だろう。なお、「ヴァナキュラー」とは、「土着の」「根付いた」等の生活基盤(少数民族の言語や土地等)を意味する言葉であるが、「ヴァナキュラーなもの」とは、制度に他律されず、自律性があるものとして、イリイチが再定義した言葉である[8]。
これらの批判は、美術的な制度から離れ、後述する産業文明批判という視点から見れば、その批判をあまり気にする必要もないように感じる(前編で述べた通り、ルアンルパは西欧的な制度の文脈に乗らないことを明言している。)。
2「イヴァン・イリイチ」と「コンヴィヴィアリティ」
(1)「イヴァン・イリイチの思想」とは?
イリイチの思想は、古びた思想だといわれることもあるが、筆者は、むしろ、イリイチが生きた時代よりも「テクノロジー」と「制度」の力がさらに強まる現代にこそ、重要となる思想であると考えている。
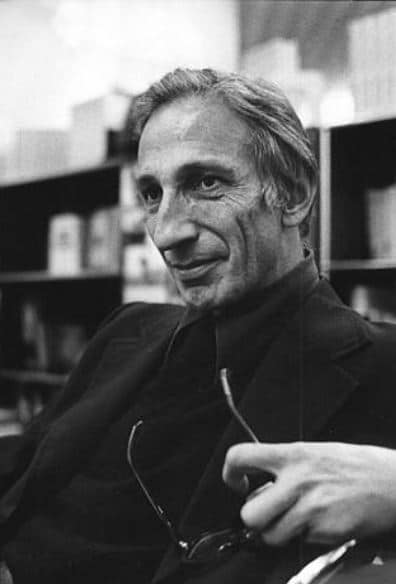
イリイチは、キリスト教世界のエリートであったにもかかわらず、西欧世界から南米に渡り、非西欧の世界から産業文明を批判し続け、「人間の生き方」「生きる希望[10]」を問い続けた哲学者である。筆者もアジア途上国で法律事務所を運営しながら、イリイチの思想に共感することが多い。SDGsや個人情報保護等の「公共」の名を借りた多くの商品やサービスに辟易し、今やっていることが、イリイチが定義した「逆生産(counter-productivity)[11]」に陥っている自覚がありながら、そのようなサービスや提案を行ってしまう。その他「シャドウワーク(shadow-work)」や「経済セックス(economic sex)」等の重要概念は、紙面の関係上、詳述はしないが、イリイチは、現代産業社会の生きづらさの深層を示すヒントを与えてくれる。
イリイチは、社会的サービスの背後にある「制度」や専門家の「権力」が、人間の自己家畜化を推し進める要因になっていると指摘している。学校を一つの例として挙げると、学校という「制度」が人間の自由を制限し、人間の自律性を喪失させていくと述べた(ここでは詳述しないが、イリイチは「脱学校論(deschooling)」を展開している。)。このような社会から人間性を取り戻すために、学校をはじめ、交通や医療等の社会サービス等の「制度」を批判した[12]。
また、イリイチが注目したのが「制度」を含む「道具(tool)」の概念である。「道具」には、「制度」や「テクノロジー」等によって他律される機械のようなパワー・ツールに対して自律的に手を使うハンド・ツールがあると述べる。現代社会においては、他律的なパワー・ツールが思考や社会を支配する状況に至っているが、「道具(ハンド・ツール)」を捉え直しながら、その支配に対峙し、そこから脱却しなければならないと主張する[13]。このイリイチの思想は、後述するルアンルパの実践等と大きく重なる部分があると考える。
(2)「コンヴィヴィアリティ(コンビビアリティ)」とは何か?
–各人のあいだの自立的で創造的な交わりと、各人の環境との同様の交わりを意味させ、
またこの言葉に、他人と人工的環境によって強いられた需要への各人の条件反射づけられた反応とは
対照的な意味をもたせようと思う–
――イヴァン・イリイチ『コンヴィヴィアリティのための道具』より[14]
さて、本題の「コンヴィヴィアリティ(conviviality)」とは、イリイチが産業文明批判の観点から定義した言葉である。「コンヴィヴィアリティ」とは、スペイン語に由来する言葉であり、日本語では「自立共生」と訳されることが多いが、ラテン文化を踏まえると、厳密には「共生」ではない。イリイチ研究者の山本哲士氏[15]の言葉を借りれば、「自立」と「共生」とは、ある種矛盾する言葉であるが、この「相反性」がイリイチ理解の要であり、「コンヴィヴィアリティ」とは、「互いに相反するものが構造的に共存しあいながら、排他的ではなく、多元的に均衡しあっていること」だと述べている[16]。そのため、山本氏は「自律共働」という言葉をあてている[17]。
例えば、ある場所に、他所から来た宣教師が訪れ、そこにヴァナキュラーな暮らしする人々が集まり、その宣教師との対話の中において、その内容が、その土地の人々の新しい知恵として認識されたときに、ラテンの世界では「コンヴィヴィアルであった」という表現が日常的に使われるとのことである。つまり、相容れない他律的なものが、自律的なものとして、瞬間的に良い方向に働いたということである[18]。
実際に、筆者が知るアジアのコレクティヴは、縁深い関係というより、ある種「無縁[19]」的なサバサバとした関係を好むように感じる。メンバー自体も流動的であり、その間口は非常に広く、参加等についても、基本的に強制や制限されることもない。自律的な個人が、他者と瞬間的かつ一時的に交わっているだけのように感じている。その意味で、別に見世物であろうとなかろうと、ドクメンタの出展アーティストが、カッセルにおける「他者」との間で、「コンヴィヴィアル」な偶然かつ一時的なよい状態が生み出せればよいだろうし、また、「関係性の美学」の論争についても、そもそも「安定的な共生」関係を志向していないと考えれば、この批判もあたらないのではないだろうか。
(3)「コンヴィヴィアリティの道具」を回復するための「技法」
そして、イリイチは、「コンヴィヴィアリティのための道具」を取り戻すためには、①科学の非神話化[20](過剰な科学的知識への信頼からの脱却)、②言葉の再発見[21](産業文明主義的な言葉の利用からの脱却)、③法的手段の回復[22](自身が公的な手続きに関与しているという自覚を回復すること)、この3つの要素が必要であると述べている。
「科学の非神話化」については、前半における「脱人間中心主義」や「再魔術化」の議論で既に十分述べられていると思うので、ここでは省略する。
「言葉の再発見」と「法的手段の回復」に関しては、「プロジェクト型民主主義」という概念が重要となると考えている。「プロジェクト型民主主義」とは、イタリア人思想家のエツィオ・マンズィーニが定義する言葉であるが、その場所のコモンズ(ちなみに、コモンズは、イリイチの主要概念の一つである。)とそれを管理する信託関係を生み出すために、自律的な人々がアイデアとプロジェクトを持ち込み、絶えず対話を継続しながら、意思決定を行うようなプロセスであると述べられている[23]。これは、ルアンルパの実践やインタビューから垣間見えることと重なり合う。
まず、「言葉の再発見」について、イリイチは、現代の言葉は、産業文明社会によってラディカルに独占(radical monopoly)されており、この社会では、ほとんどの言葉は、所有的な言語で用いられていることから、行為的な言語用法からこれらを見直していく必要があると指摘している[24]。例えば、学校で「教育サービスを得る」のではなく学校で「何かを学ぶ」、駅で「公共輸送サービスを得る」のではなく駅から「どこかに移動する」、役場で「職を持っている」のではなく職場で「仕事する」といったように行為的な言語用法に転換していく必要がある。しかしながら、現在の教育制度において、「私は学びたい」という言い方は、「私は教育を受けたい」という言葉に自然と転換されている。そこで、私達は、一度「制度」から距離を置き、プロジェクト型民主主義的プロセスを通じ、これらを見破り、自律的な言葉の用法を取り戻す必要があるのではないだろうか。前編で述べたルアンルパの対話実践は、まさに「言葉の再発見」のためのプロセスであり、そのための場所は、いわゆる堅苦しい会議室ではなく、後述する食事場、カラオケ場やサウナ等、人々が集まる場所でなければならないのであろう。
次に、イリイチは、「法的手段の回復」に関して、司法制度や警察権力についても産業文明を迎合する他律的な道具なってしまっていると述べる。そこで、選挙制度等の既存の政治的過程を経る法律や形式とは別次元の道具として、「適切な法的手続き」を自分のもとに取り戻すことが重要だ、と述べる[25]。その意味でも、組織やコミュニティにおける自身の意思決定が重要となる。
この点、アメリカの人類学者デヴィッド・グレーバー(David Graeber、1961年-2020年)が述べる通り、民主主義は、西洋(アテネ)で生まれたものではなく、全会一致制が、民主主義の根幹をなす(多数決の原理に服従しない)と指摘する[26]。この点、現地で、ルアンルパのアデ、タリンパディ(Taring Padi)のアレクサンダー・スパトノ(Alexander Supartono)へのヒアリングを行ったところ、基本的には、組織の意思決定については、多数決の方式を取らず、全会一致の方式を取っているとのことである。すなわち、非合理的かもしれないが、各人が意思決定をしなければ、意思決定プロセスが進行しないということである。彼らがイリイチを参照しているかは不明だが、このプロセスこそが、人間の「法的手段の回復」に対応する実践であると考える。


1998年に結成されたインドネシア・アートコレクティヴのタリン・パディは、スハルト政権に反対する運動から生まれたアート・コレクティヴである。独裁政権に対抗するために、木版画、ポスターや壁画等を展開する[27]。なお、フリデリチアヌム広場の「People Justice(民衆の正義)」は、反ユダヤ主義に関する問題で覆い被され[28]、撤去されたことは、「表現の自由」に巡る大きな波紋を呼んでいる。
なお、タリン・パディについて「農業×アートコレクティヴ -糸島芸農から学ぶ(後編)-」にて、江上賢一郎氏が詳述している。
それ以外にも、ルアンルパの活動は、イリイチの「貨幣社会批判」や「脱学校」とも通じるところがある。例えば、彼らの作品の一部は、ドクメンタの自動販売機で販売されているが、そこでは値段が決まっておらず、購入者の意思に基づいて、寄付金として支払われるというものもあった。また、アデによれば、これらの売上は、ルンブン(米蔵)に貯蔵され、全体に還元される仕組みとなっているようだ。ルアンルパのメンバーと話していて、「マーケットやギャラリーがつけるアートの価格はよくわからない。ここにある小さなアートなるものに目を向けて欲しい」という言葉が記憶に残っている。いわゆるギャラリー等で販売されるものではなく、日々の生活や表現の中で生み出され、普段使われる「道具(ハンド・ツール)」に価値を感じ、自分達の自律的な生活を取り戻して欲しいということではないだろうか。




また、ルアンルパの目線は、「学びの場」にも熱く注がれている。それは、フリデリチアヌム美術館の1階というドクメンタにおいてもっとも重要な場所に、遊具施設、制作施設、図書施設、託児所や学習スペース等を配備したルル・キッズ(RURU KIDS)を配置していることからも明らかだろう。




また、同じくフリデリチアヌム美術館の1階のグッドスクールの入り口の展示キャプションは、驚くべきことに、基本的に子供目線の高さに揃えられている。そこには、読書のための場所、対話のための場所、遊技場、縫製設備等のハンドツールを利用できる場所等、グッドスクールにおける実践の内容が整理されている。




さらに、フリデリチアヌム美術館2階では、Asia Art Archive、The Black Archives、Archives des lutes des femmes en Algerie等のアーカイブ展示が行われていた。アーカイブは、過去と現在を繋ぎ、ヴァナキュラーな場所とその地に生きる人々の現在地を理解する上で、重要な機能を果たすのだろう。


以上のルアンルパの実践からも明らかな通り、ルアンルパは、既存の「制度」を超越して、オルタナティブな「自ら学ぶ」場所や「自らプロジェクトを行う」場所を生み出すことが、産業文明を乗り越える上で、もっとも重要だということを強く認識しているのだろう。それが美術的な文脈から逸脱していようが、身内のサークル的といわれようが、「コンヴィヴィアル」な瞬間が生み出されるのであれば、特に「制度」や「テクノロジー」の力が強まっている現代(筆者は少なくともそのように感じている。)には、その実践的な価値が許容されてもいいのではないだろうか。


(4)「ともに生み出す」という技法
最後に、「コンヴィヴィアリティ」には、「自律共働」という言葉があてられているが、「共働」とは何を意味するのだろうか。筆者は、今までの議論を踏まえると、「自己と他者という相反するものが構造的に共存し、多元的に均衡しあいながら、何かを『ともに生み出すこと』」ではないかと考えている。ドクメンタの展示を見て感じることは、誰でも、どこでも何かを「生み出せる」ということである。つまり、「アート」という技法を使えば、別に特権階級やいわゆる天才でなくとも、制作や、表現することは当然に可能である。ドクメンタの作品群は、全てが「コンヴィヴィアル(自律共働)」な状態で生み出されたものとはいえないかもしれないが、ドクメンタでは、自己と他者が「コンヴィヴィアル」に生み出す集団的な技法や実践について、好例が多く示されていた。
例えば、カンボジア・アートコレクティヴのササアートプロジェクト(Sa Sa Art Projects[29])のメンバーは、基本的に専門的な美術教育を受けていないメンバーが主体となって運営されている。コンセプトメイキングとペンディング等の制作は、分業体制になっていることが多く、全員が自律したアーティスト、リサーチャー、キュレーターでありながら、各々の強みを基礎に、対話による共働がなされている。展示においても、キュレーターという存在は特に明示されず、自律した他者を巻き込みながら、「ともに制作し、ともに展示をつくる」という特性が発揮されている。

「Popil」Khvay Samnang
プノンペンでも展示が開催されていた「Master of Land and Water」展のドクメンタ版である。筆者がコレクションしているKhvay Samnangの「Popil」とLim Sokchanlinaの「Letter to the Sea」が展示されていた。また、Sa Sa Art Projectsの他者との緩やかな関係を示す例として、過去Sa Sa Art Projectsのレジデンスに参加予定のベトナム人アーティストのNgoc Nauや過去参加経験のあるミャンマー人アーティストのAung KoとNge Nayの作品が展示されていた。恐らく「何を見ているかわからない!」と批判されるドクメンタにおいて、比較的、見やすい展示だと思われたのではないだろうか。

「Letter to the Sea」Lim Sokchanlina

「Ritual Objects」Ngos Nau

「Printemps 21」Nge Lay
他方、バーン・ノーク・コラボレイティヴアート&カルチャー(Baan Noorg Collaborative Arts and Culture)[30]は、スケート場を展示の中心に置いている。バーン・ノークは、タイのノンポ―(Nongpho)にある村の名前であり、その場所で展開するアートコレクティヴである。バーン・ノ―クは、タイ語でBaan(バーン)は「家」、Noorg(ノーク)は「外」を意味し、「内/外」の関係を思考しているように感じる。本展示では、ドクメンタにやってきた一時だけともにスケートを楽しむ他者が作品の重要な要素となっており、一時の他者と「ともに生み出され」る展示ではないだろうか。


叙事詩ラーマヤナに関する乳牛の物語を起点として、ウミガメの背中にある仏塔やタイの冠婚葬祭においてよく見る照明等とともに、中心には海に見立てたスケート場が設置されている。そこに見知らぬ地元のスケーター達が集まってスケートをしている様子は、場所と時間を超えて「伝統/流行」や「内/外」等について思考する機会を与える。
また、特に興味深かったのは、アグス・ヌル・アマル(Agus Nur Amal)の実践である。アグスは、インドネシア・アチェ出身の俳優であり、語り部である。アグスは、フライパン、洗濯バサミやゴミ袋等の日常使いする「道具(ハンド・ツール)」を使いながら、アチェの神話や伝説をユーモアたっぷりに語る。そして、それらの「道具」を使って、子供のおもちゃなのか、椅子なのか、街灯なのか、あるいは作品なのか、それらの境界を超えた「アートなるもの」を生成する。すなわち、「アートとは、誰でも制作でき、楽しめるものなのだ」ということを改めて気付かされた。

インドネシアの様々な場所で、政治、環境、農民の生活等の講演を行っている。土着の小説や伝説等を踏まえて、アグスが面白おかしく話す様子と観客の応答を示す映像やその場で制作されたであろう日常品を使ったインスタレーションは、日常を自分たちの手で楽しむためのヒントに溢れていたように思う。



他方、キリ・ダレナ(Kiri Dalena)は、フィリピン出身のアーティストで、フィリピンにおける不正義や社会的な不平等をテーマにした作品で知られる。また、彼女自身もアートコレクティヴを運営しつつ、フィリピン国内の声を集めるかたちで抵抗活動を行っている。ドクメンタで展示されていた「Pila」も見知らぬ他者達と「ともに生み出さ」れた作品という射程に入るだろう。

キリへの現地でのヒアリングによれば、展示作品のPilaは、彼女の自宅の前に設置した5台のカメラを使った映像作品であり、通りを歩く他者の音声と普段の生活の様子を再整理したものである。コロナ渦における集合的な意識や無意識を提示している。

最後は、今回のドクメンタ滞在中において、もっとも長く滞在した場所であるニャサン・コレクティヴ(Nha San Collective[31])の活動に目を向ける。ニャサン・コレクティヴは、2013年にベトナム・ハノイで立ち上がったアート・コレクティヴである。「Nha San」は、モン族の伝統的木造家屋を意味し、またベトナム初の現代アートスペースとして非常に重要な場所であった「ニャサン・スタジオ(Nha San Studio、2011年に当局の指導により閉鎖を余儀なくされる)」に因んでいる。ニャサン・スタジオは、グエン・マン・ドゥック(Nguyen Manh Duc)とキュレーターのチャン・ルーン(Tran Luong)によって、1998年に設立され、今はグエン・マン・ドゥックの娘であるグェン・フォン・リン(Nguyen Phuong Linh)がその意志を引き継いて運営を行っている[32]。


ドクメンタ会場のWH22には、ベトナム戦争時代に離散したベトナム難民、移民やその子供達のための庭(!)が存在していた。ニャサン・コレクティヴの創設者の一人であるテゥアン・マミ(Tuan Mami)は、2022年2月からカッセルに入り、この庭を作りはじめた。もはや庭だけではなく、食堂や宿泊施設まで手作りで作られており、そこには20名弱のメンバーが生活していた(!!)。そこで採集された野菜や果物を食し、実際に生活していた。「ここは果たしてカッセルなのか」と目を疑った。マミは、苦労して持ち込まれたベトナムの植物たちをこの庭に植え、丁寧に育てている。これはベトナム戦争時代に、ある種不合法な方法で、ドイツに逃れてきたベトナム難民と重なり合う。ニコラ・ブリオーが述べた「ラディカント(radicant、概念については後編で詳述予定)[33]」なベトナム系難民は、その庭で成長する植物のように力強く、ドイツという土地に根を張っている。そして、その庭に人間/植物の境界を超えて集い、生成された諸存在は、力強く自律的に生きているのだ。筆者は、その姿に感動してしまい、その場所から、なかなか離れることができなくなってしまった。これはベトナムの人達のみならず、植物や自然と「ともに生み出され」た素晴らしい実践であると感じた。

緑豊かな植物の中からテゥアン・マミが現れた。これらの植物は、ベトナムという故郷の野菜やハーブであるが、ドイツにベトナムの植物や野菜を持ち込むことはとても難しく、これらの懐かしい食に触れることもままならないという。人類の歴史において、人間、動物、そして植物はともに移動してきたのに、なぜ現代においては、それが許されないのか。植民地時代においては、西欧世界は、サトウキビ等の植物を輸出し、多大なる富を得たというのに、という彼の問いが記憶に残る。移動と離散を繰り返す少数民族モン族の家(ニャサン)に来たような感覚、そして、私が熊野の森で生きる炭焼の家に訪問し、対話したときの感覚と重なるような気がするのは、少なくとも勘違いなどではなさそうだ。



ニャサン・コレクティヴの好例を踏まえても、「植物(みかん)を栽培すること」は、よく生きるための技法なのである。みかんコレクティヴでは、この体験を活かし、今度は私達が他者として、ヴァナキュラーな場所とそこに生きる人々とともに、「コンヴィヴィアル」な良き状態を生み出せるよう展示やワークショップの準備を進めていきたい。
さて、後編では、ニャサン・コレクティヴの実践にあるように「植物」の存在が注目されつつある。ここまで述べてきた議論、ビエンナーレとドクメンタの両展示の内容を踏まえ、もう一歩進んで、動物系の限界と、紀南/熊野の持つ「植物系」の可能性と人間/植物との絡まり合いについて考えていくことにしよう。
以 上
[1] Documenta 15 Review: Who Really Holds Pwer in the Artworld
https://artreview.com/documenta-15-review-who-really-holds-power-in-the-artworld-ruangrupa/
[2] Documenta Drama: the sic most controversial (and confusing) Things we saw at the Kassel exhibition
https://www.theartnewspaper.com/2022/06/21/documenta-15-most-controversial-kassel-exhibition
[3] BAH LUMUNG https://www.artforum.com/diary/kristian-vistrup-madsen-at-documenta-15-88761
[4] Documenta fifteen Official Guidebook, 9頁
[5] 山本浩貴『脱植民地化の技法(アート):東アジアのポストコロニアルな文脈におけるソーシャリー・エンゲージド・アートの可能性について』https://note.com/misonikomi_oden/n/n615ecc796b1e
[6] ARToVILLA『アートをつくらずに、友達をつくろう。ドイツ国際美術展「ドクメンタ15」への挑戦/「居場所のかたち」栗林隆インタビュー』、2022年5月27日、https://artovilla.jp/articles/takashi-kuribayashi-interview.html
[7] 星野太著『美学のプラクティス』水声社、2021年、122、123頁
[8] 山本哲士著『イバン・イリイチ―文明を超える「希望」の思想』2009年、文化科学高等研究院出版局、64頁
[9]ウィキペディア「イヴァン・・イリイチ」
[10] デイヴィッド・ケイリー編、臼井隆一郎訳『生きる希望 -イバン・イリイチの遺言-』藤原書店、2006年
[11] 制度がその目標として掲げたことに反する結果を生み出すこと(山本哲士著『イバン・イリイチ―文明を超える「希望」の思想』2009年、文化科学高等研究院出版局、79頁)。例えば、学校に行けば、学ぶモチベーションが減退したり、病院に行けば病気が逆に生み出されたり(医原病)、交通が高速化されれば、渋滞などが生じて、移動時間がさらに伸びる状態等の事象が挙げられる。
[12] 山本哲士著『学校・医療・交通の神話 現代産業社会批判 -コンビビアルな世界へ-』、2021年、文化科学高等研究院出版局、9−14頁
[13] 山本哲士著『イバン・イリイチ―文明を超える「希望」の思想』2009年、文化科学高等研究院出版局、74-78頁
[14] イヴァン・イリイチ著、渡辺京二、渡辺梨佐訳『コンヴィヴィアリティのための道具』、39、40頁
[15] 山本哲士著『学校・医療・交通の神話 現代産業社会批判 -コンビビアルな世界へ-』、2021年、文化科学高等研究院出版局、346頁 同書では、「イリイチ専門家」ということについて、山本氏が述べている。詳細は同書を参照して頂きたい。
[16] 山本哲士著『イバン・イリイチ―文明を超える「希望」の思想』2009年、文化科学高等研究院出版局、209頁
[17] 山本哲士著『学校・医療・交通の神話 現代産業社会批判 -コンビビアルな世界へ-』、2021年、文化科学高等研究院出版局、321-329頁
[18] 同書、74頁、75頁
[19] 網野善彦『無縁・公界・楽 -日本中世の自由と平和』、平凡社、1996年
[20] イヴァン・イリイチ著、渡辺京二、渡辺梨佐訳『コンヴィヴィアリティのための道具』、190-195頁
[21] 同上、195−202頁
[22] 同上、203-217頁
[23] エツィオ・マンズィーニ著、安西洋介、八重樫文訳『日々の政治 ソーシャルイノベーションをもたらす デザイン文化』ビー・エヌ・エヌ新社、2020年、159-161頁
[24] 山本哲士著『イバン・イリイチ―文明を超える「希望」の思想』2009年、文化科学高等研究院出版局、229頁
[25] 山本哲士著『イバン・イリイチ―文明を超える「希望」の思想』2009年、文化科学高等研究院出版局、230頁
[26] デヴィッド・グレーバー著、片岡大祐訳『民主主義の非西洋起源について―「あいだ」の空間の民主主義』、以文社、2022年、43-47頁
[27] 廣田緑『現代美術の新たな戦略:アートコレクティヴ―アーティストが組織をつくるとき―』、104、105頁 https://rci.nanzan-u.ac.jp/jinruiken/publication/item/ronshu6_05%20Hirota.pdf
[28] 「ドクメンタ15が反ユダヤ問題で批判を受けた展示作品を覆い隠す。止まらない“表現の自由”をめぐる騒動」ARTnewsJAPAN, 2022年6月24日 https://artnewsjapan.com/news_criticism/article/280
[29] アウラ現代藝術振興財団『リノ・ブース:カンボジアの現代アートを支えて10年』
[30] Baan Noorg Collaborative Arts and Culture ウェブサイト(https://www.baannoorg.org/)
[31] Nha San Collective ウェブサイト(http://nhasan.org/)
[32] ベトナムにおける現代アート史やニャサン・コレクティヴに関する歴史や活動の系譜は、江上賢一郎によるインタビュー「ハノイにおける「現代アート」受容と2つの「ニャサン(家)」」が詳しい。http://scene-asia.com/ja/archives/692
[33] ニコラ・ブリオー著、武田宇也訳『ラディカント―グローバリゼーションの美学に向けて』フィルムアート社、2022年

