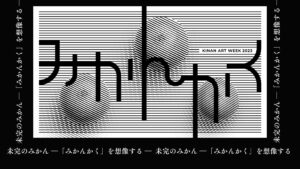みかんコレクティヴ

みかんと人間の芸術人類学 (中編)
-「みかんマンダラ」展を終えて-
2 みかんと人間の境界を越えて
(1) 実り / 果実を巡る旅
地元農家が共同出資で設立した「秋津野直売所きてら」に隣接する「ゆい倉庫」では、地域で生産された柑橘類などが加工され、様々な加工品が販売されています。地域の生産者の方々のもとで実った果実が集められ、加工・販売されるこの場所は果実の一つの「おわり」の場所ともいえます。しかしながら、私たちが食すことで「みかんの旅」は終わるのではなく、身体を通して、人間を含めた生命体の大きな循環や流動の「はじまり」でもあるように思います。


人類学者のティム・インゴルド(Tim Ingold、1948-)は、「生きていること(Animacy)」とは、「精神と物質という分割線を引く以前の、物事の途切れることのない生の流れそのもの」であり、「生をいかなる境界も設定しない生成の連続」と述べています[奥野、山口、近藤2012:52、53]。つまり、「生きていること」とは、生命体の動きの中に身を置いて、その素材として、「はじまり」も「おわり」もない、その流動世界に参加することなのです[インゴルド2021:167−171]。
人間とみかんは、常に生きとし生けるものとして漂流し続けています。そのわかりやすい例が、食事です。「食べること」は、「食べるもの」と「食べられるもの」が重なり合い、その境界を溶かそうとする行為であり、私達にとって食べることは、常に他の生きものに出会うこと、他者の生によって生きるように強いられ、他者の生を自分の身体に注入することを意味しています[コッチャ2022:97]。その意味で、果実として食べられるという「死」は、一個の生命体の終わりを意味するものではなく、新たな生の一部になることなのです。ゆい倉庫では、鑑賞者に対して、充満するその香りとともに、みかんが配られました。私たちは、みかんを食べることによって、「みかん」の「生」を取り込んでおり、「人間」と「みかん」の境界が揺らぐ体験を生じさせました。

また、会場では、廣瀬氏による柑橘類などを用いた『官能の庭(il giardino dei sensi)』、みかんジュースや摘果を用いた紙のインスタレーションが展示されました。人類は今まで、植物の存在を最底辺に置いてきました[マンクーゾ2015:32−34参照]。しかし、『官能の庭』では、人間よりも大きな木箱を用いることによって、柑橘の木に見おろされます。廣瀬氏は、普段農家の方が体験しているような感覚を可視化することによって、「人間」と「みかん」の関係をひっくり返そうとしている(フラットにしよう)のではないかと思いました。
日本の俳句文化においては、必ず「季語」が求められます。これを現代的に表現しているのが、『官能の庭』であったかもしれません。つまり、俳句において「季語」が求められるのは、表現者が、人間以外の視座から思考するためだといわれています[中沢、小澤2016:16]。この文脈を踏まえると、『官能の庭』は、みかんと人間の視点の交換するための媒介のようなものではないかと思えます。
さらに、様々な場所から集められた多くの種類のみかんジュースは、その色合い、濁り方、ボトルのかたちも様々です。少し離れたところから、インスタレーションを見ると、自然物と人工物の境界にある「みかんジュース」に個性らしきものが見出されるような気がします。
柑橘農家では、果実の収穫前に、摘果が行われますが、廣瀬氏は、今まで農地に摘果の結果、打ち捨てられ、土壌に還っていた摘果みかんで紙を作ってみました。その紙が、まさに太郎が述べた「絨毯のような両界マンダラ」のように見えたのは、私だけではないでしょう。
廣瀬氏の黄緑一色の「みかんマンダラ」は、太郎がいう「マンダラの美」に適っていたように思います。太郎は、「マンダラは一色のモノクロームが正当なあり方」だといいます。そして、「色が一色だけの場合、直視しているうちに、無限の空間に没入して行く。一切空の場所に、あらゆるイメージの可能性がわいて出る。そしてそれは無限に消滅し、瞬間、瞬間に出発し、展開するのである。(中略)マンダラのモノクロームはニヒリズムではない。秘密への参入。絶対無としての、あくまでもかりそめの手段である。かりそめだからこそ強烈なのである。」と述べています[岡本2016:238、241参照]。まさに太郎がいうように、この「みかんマンダラ」は、かりそめの姿なのであり、みかん、紙もみかんジュースも、地域の人々に食べられ、飲まれ、配り配られながら、無色透明なマンダラ、すなわち、「無」の世界に還っていくのです。
そして、廣瀬氏は同時に「みかんの苗木の旅」と題した長期プロジェクトを開始しています。オープニングセレモニーでは、廣瀬氏と紀州原農園の原拓生氏による説明会が行われました。原氏は、江戸後期から続く秋津地域の農園の七代目園主であり、特に、柑橘の持つ多様性や深い歴史に関心を持ち、最新の品種だけでなく原種と呼ばれるような希少品種、地域に根差した古くからの品種を含む約60品種の柑橘を栽培している柑橘の栽培技術と柑橘の文化を繋げる柑橘農家です。廣瀬氏と原氏は、みかんの苗木を田辺市や紀南在住の参加者(=里親)と共に育て、将来的には「コモンズ農園(誰でもが利用できるみんなの農園)」としての新しい農地と「共有すること」のあり方を考えます。


「みかんマンダラ」は、「無に還っていく」と述べましたが、純粋贈与は「無」に支えられている贈与であり、贈与社会は「無」によって動かされていた社会なのです[中沢2004:285]。「コモンズ農園」の展開が、破壊や消費の先にある「純粋贈与」に支えられた贈与を基礎として、市場原理や資本主義のあり方を越えていく長期プロジェクトとして、「対称的な思想」を育む場となることを願っています。


(2) 土と根 / 見えない根を探る
かつて田内栄一が1957年に市の文化発展のために田辺市古尾に建てた旅館「愛和荘」は、数多くの国内外の著名人が訪れるなど、地域の文化交流の拠点でした。現在はその屋号を引き継ぎ、上野山城跡の古民家を利用した旅館として運営されています。私たちは、田辺市街と田辺湾を見渡せる場所から、地中にある根とその土を知覚することで、豊かさを生み出す土壌に注目しました。
本会場では、廣瀬智央、ジェームズ・ジャック/南条嘉毅/吉野祥太郎によるBacilli(バシライ)、クワァイ・サムナンによる3作家の展示を行いました。


廣瀬氏の新作の『クマノ・ラディーチ(Kumano Radici)』は、廣瀬氏が熊野古道を歩き感じた、自然や樹々の根をモチーフとした彫刻と写真から構成されています。特に、不可視の存在である「根」をどのように捉えるか、ということに思考を重ねてきました。
地上に現れた根の意外な「軽やかさ」に驚くとともに、根を多面的に見たり、見上げたりする行為は新鮮だったのではないでしょうか。また、写真作品において、根は、地下に向かって伸びているのか、もしくは、天体に向けて伸びているのか。まさにコッチャが『植物の生の哲学(2019)』で述べた、「根は天体である[コッチャ2021]」という言葉と重なり合うように、岡本太郎がいう熊野の「反の世界」[岡本2015:142]がよく示されているようにも思いました。


また、カンボジア人アーティストのクワァイ・サムナン(Khvay Samnang、1980-)は、象徴的な身振りで、伝統的文化儀式、また、歴史や現在の出来事について、新しい視点を提示します。『無題2011(Untiled 2011)』では、開発が進むボンコック湖が映し出されます。プノンペンでは、加速する土地開発によって、2008 年以降ボンコック湖とその他いくつかの主要な湖沼地帯が、どこかからやってきた土によって埋め立てられています。他方、カンボジアの土は、埋立地用にシンガポール等の先進国に輸出されており、実は、「場所」を構成する土も移動をし続けていることも忘れてはいけません。


その土に絡む問題として、開発による低所得者層の追い出し、雨季の河川の氾濫と汚染、土地の過剰消費によって引き起こされる問題は、プノンペンに限らず、土は誰の物であるのかという普遍的な問いを投げかけます。その意味で、愛和荘から見える田辺湾の美しい景観は、古来、田辺という土地は、誰がどのように形作ってきたのかということを改めて考えさせてくれます。
そして、10月7日には、芸術人類学者・石倉敏明氏をお招きし、サムナンとのトークセッション「土と根の記憶―カンボジアと紀南/熊野から」を開催しました。石倉氏は、インドや日本中を旅しながら、日本の伝説、民俗や神話を調査し、多くの研究発表を行っています。両者の対話を通じて、カンボジアと紀南の隠された記憶、物語や神話の共通性や相違をあぶり出していきました。
フランス人哲学者のシモーヌ・ヴェイユ(Simone Weil, 1909-1943)が述べる通り、人々にとって、自身の根(ルーツ)や土(居場所)を持つことは、もっとも根源的な欲求です[ヴェイユ2010:64]。サムナンの作品を起点にしながら、カンボジアと熊野の神話、西洋のダンスと東洋の舞踏、植物と動物等の表現の差異と類似からカンボジアと紀南の根や土について語り合いました。サムナンの言葉、詩やダンスから、植物と動物、精神と物質などを切り分けておらず、矛盾律を越えた神話思考が彼の基礎にあり、その表現が構築されているという直感を得られたことが、重要な収穫であったように思います。トーク中に行われたサムナンの即興の詩やダンスは、言葉や言語を超えて、熊野の地と繋がる「何か」を感じさせてくれました。


また、バシライは、土・人・食にフォーカスしたアート・コレクティヴです。バシライとは、土に繁殖する生物の分類の一つであり、菌や藍藻などの一般的な細菌、バクテリアを指し、人間とそれらを繋ぐ役割として空間・環境を創造しています。バシライの活動は、場所の記憶を地中に根を張るように、土を巡る物語を蘇らせようとするのが、その特徴です。
今回、紀南在住の南条を中心に、田辺のフレンチレストラン「caravansarai」の更井シェフと協働しながら、「土のレストラン」をオープンしました。10月14日には、「薫る土壌」と銘打った食事会を開催し、地域の人たちと、果実と土の境界を越えて、「食べることとは何か」、「農業とは何か」、「土とは何か」、「場所とは何か」ということを改めて考え直す場を生み出しました。
田辺市内の万呂や上芳養などの様々な地域の柑橘農家の農園の土と併せて、果実や根なども持ち寄り、視覚のみならず、嗅覚や味覚を通じて、その違いを楽しみました。また、この「薫る土壌」の映像記録は、2023年にバシライの新作として発表し、併せて、柑橘の食事会やワークショップも開催する予定となっています。





<参照文献>
- C.G. ユング(著)、林道義(訳)、『個性化とマンダラ』みすず書房、1991年
- エマヌエーレ・コッチャ(著)、山内志朗(訳)、『植物の生の哲学:混合の形而上学』、勁草書房、2019年
- エマヌエーレ・コッチャ(著)、松葉類、宇佐美達朗(訳)、『メタモルフォーゼの哲学』、勁草書房、2022年
- クラリッサ・ハイマン(著)、大間知知子(訳)、『オレンジの歴史』、原書房、2016年
- シモーヌ・ヴェイユ(著)、冨原眞弓(訳)、『根をもつこと(上)』、岩波文庫、2010
- ステファノ・マンクーゾ、アレッサンドラ・ヴィオラ(著)、久保耕司(訳)、『植物は<知性>を持っている』、NHK出版、2015年
- ティム・インゴルド(著)、柴田崇、野中哲史、佐古仁志、原島大輔、青山慶、柳澤田実(訳)、『生きていること 動く、知る、記述する』、左右社、2021年
- デイビット・モンゴメリー(著)、片岡夏実(訳)、『土と内臓 微生物がつくる世界』、築地書館、2016年
- ニコラ・ブリオー(著)、武田宙也(訳)、『ラディカント グローバリゼーションの美学に向けて』、フィルムアート社、2022年
- ピエール・ラスロー(著)、寺町朋子(訳)、『柑橘類の文化誌』、一灯舎、2010年
- フロランス・ヴュルガ(著)、田中裕子(訳)『そもそも植物とは何か』、河出書房、2021年
- 安藤礼二(著)、『縄文論』、作品社、2022年
- 奥野克巳、山口未花子、近藤祉秋(編)、『人と動物の人類学』、春風社、2012年
- 岡本太郎(著)、『神秘日本』、角川ソフィア文庫、2015年
- 紀南アートウィーク ケミストリーセッション Vol.2 「籠もるとひらく―知の巨人・南方熊楠と現代アート―」、11月20日閲覧(https://kinan-art.jp/info/930/)
- 三木成夫(著)、『胎児の世界』、中公新書、1983年
- 山本哲士(著)、『古事記と国つ神論:日本国の初まりと場所神話』、EHESC、2022年
- 森元斎(著)、『アナキズム入門』、筑摩書房、2017年
- 頼富本宏(著)、『密教とマンダラ』、講談社学術文庫、2014年
- 石倉敏明、唐澤太輔「外臓と共異体の人類学」、2020年、EKRITSウェブサイト、11月20日閲覧(https://ekrits.jp/2020/12/3980/)
- 中沢新一、「ユングと曼荼羅」、日本ユング心理学会(編)、2010年
- 中沢新一、小澤實(著)、『俳句の海に潜る』、角川書店、2016年
- 中沢新一(著)、『芸術人類学』、みすず書房、2006年
- 中沢新一(著)、『純粋な自然の贈与』、せりか書房、1996年
- 中沢新一(著)、『対称性人類学』、講談社、2008年
- 中沢新一(著)、『東方的』、講談社学術文庫、2012年
- 藤原辰史(著)、『植物考』、生きのびるブックス、2022年
- 藪本雄登、「みかんコレクティヴ:内なるみかん ひらくオレンジ」、2022年11月20日閲覧(https://kinan-art.jp/info/5785/)
- 藪本雄登、「みかん神話-紀伊半島と橘の関係を思考する」、11月20日閲覧(https://kinan-art.jp/info/6962/)
- 藪本雄登、「紀南という“場所” -モダニズムとアニミズム-」、紀南アートウィーク2021 公式カタログ、2022年