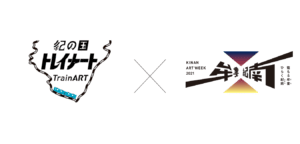コラム

熊野とゾミア -アピチャッポン・ウィーラセタクンの表現を起点に-
紀南アートウィーク 藪本 雄登
1 はじめに −アピチャッポンは、現代のシャーマンか−
―わたしは、タイ東北部にあるコーンケンという町の出身ということもあって、タイのなかで自分自身が “少数民族” みたいな気持ちで生きてきました。それは現代になっても変わらないのです。タイでは統治機構も権力もみなバンコクに集中していて、また自分がゲイということもあり、自分が中央に対して“辺境に位置している人間”だという認識を持ってきました[1]―
――アピチャッポン・ウィーラセタクン『アピチャッポン、全長編映画を語る』
タイ・チェンマイのインド料理店で、アピチャッポン・ウィーラセタクン(Apichatpong Weerasethakul、1970年生まれ)とはじめて出会った。カンヌ映画祭で4冠を得たアジアを代表する映画監督であるにもかかわらず、親しみやすく、そして、その自然体な雰囲気に驚いた。アピチャッポンから滲み出る親しみは、彼が生まれ育ったタイ東北部(イサーン)の豊かな山々や河川等の自然と無関係ということはあるまい。
ただ、アピチャッポンは、タイや周辺国に関する政治的な話となると、言葉に急に熱を帯び始める。それはまた、イサーンの複雑な歴史[2]に由来しているように思う。タイの近代化や中央集権化の過程において、仏教国教化によってピー信仰(精霊信仰)が周縁化され、また、イサーンの小さな歴史や物語は、改変、抹消されてきた事実がある[3]。
アピチャッポンの作品表現に触れる際、筆者は直感的に故郷・熊野を思い出す。哲学者の梅原猛(1925年-2019年)は、熊野をアイヌ、琉球とともに、縄文文化の面影を色濃く残す日本の原郷だ[4]、と述べているが、その根源はどこにあるのだろうか。熊野が、その多様な信仰や神話を生み出してきたのは、「山海近至」といわれる特殊な地理的条件と森、樹々、重畳たる山々、黒潮寄せる海岸、海山を繋ぐ河川等の自然環境に関連があるのは間違いない[5]。
この直感を我々に喚起させるアピチャッポンは、現代のシャーマン[6]ではないだろうか。彼の表現は、眠りを誘いながら(筆者は、上映中のどこかで必ず眠りに入る。)、前世や来世に関する想像力を喚起し、魂の存在を炙り出す。それだけでなく、不可視であった精霊や亡霊、その土地の記憶も浮かび上がらせる[7]。アピチャッポンの世界観には、「死と再生」を司る熊野のシャーマニズムと繋がる“何か”があるように思えてならない。

2 熊野とゾミア
熊野とイサーンを繋ぐのは「ゾミア」という言葉ではないだろうか。「ゾミア」とは、チベット語やミャンマー語で高地人を意味する「Zomi」に語源があり、東南アジア大陸部(ベトナム、カンボジア、ラオス、タイ、ミャンマー)と中国南部の山岳地帯を意味する[8]。アピチャッポンが育ったイサーン地域も「ゾミア」の射程に含まれ、『真昼の不思議な物体(2000年)[9]』や『ブリスフリー・ユアーズ(2002年)[10]』に登場するカレン族の人達はまさにゾミア世界に住む人々である。ゾミアに住む人々は、アニミズムを信仰しながら、国家による課税、兵役、奴隷等のいかなる支配からも逃れ、分散と移動を繰り返しながら、平等主義的な社会に暮らしてきた[11]。過去に、人類学者の岩田慶治(1922年-2013年)が東南アジアにおける山地民族の生活を調査した結果、アニミズム、口承文化、小規模グループでの移動と行動、照葉樹林帯における焼畑農業等は、古代日本人の信仰と共通する[12]点が多いと述べている[13]。熊野の山間部で炭焼き職人にヒアリングを実施した限りでは、熊野にも、アニミズム信仰、移動や口承文化等、ゾミア的な特徴を有する人々が現存している。
人類学者ジェームス・スコット(James C. Scott)は、ゾミアを「陰」の地域として捉えることができる[14]、と述べている。他方、「陰」の地域といえば、古事記・日本書紀において熊野は、「根の堅州国」といわれ、民俗学者の五来重(1908年-1993年)が「死者の霊魂が集まる場所」と述べている[15]。ゾミアも熊野も、共に「陰」の地域であり、異郷のような場所である。また、神話学者・大林太良(1929年-2001年)は、日本神話は、相当の比重において、東南アジアの山地民族の話素からの影響を受けている[16]、と述べており、神話のレベルにおいても熊野とゾミアは繋がりをみせる。
加えて、ゾミアは、山や森のみならず、海や川も射程に含む広がりを持つ。モノカルチャー化する平地世界から離脱するため、海や河川等の「水のゾミア」を経由して、海のジプシー[17]として移動し続けた人達がいるという説がある[18]。熊野史家・杉中浩一郎によれば、一本の大木をくり抜いて作られた東南アジアの丸木舟が、黒潮に乗って熊野地域に流れ着くことがあったと述べられており[19]、水のゾーミ達が、熊野という「山海近至」の魅力的なアジール(避難地)を発見し、海から再び山や森に還っていった可能性がある[20]。
3 ゾミアと熊野的表現
上述で述べた通り、ゾミアと熊野は、思想的根源を同じくする可能性があるが、以下では、これらの共通性/相違性をアピチャッポンの芸術表現と熊野の文化的表現の視点から検討する。
(1)ゾミア的なアニミズム思想表現
多くの識者が指摘する通り、アピチャッポンの表現といえば、ゾミア的、即ち、アニミズム的表現が特徴的である。例えば、“モノの記憶”というものが、アピチャッポン作品ではよく取り扱われる。短編映像作品『エメラルド』(2007年)では、閉館したホテルの中で、舞い浮かぶ羽毛のようなものが過去の記憶を述べたり、最新の長編映像作品『メモリア』(2021年)では、モノの過去の記憶を読み取ることができるエルナンという男性が登場し、石や木などにレコーディングされている「記憶」を読み取り、物語が急展開を迎える。
アニミズムは、宗教や神話の成立以前より、日常生活の隅々に浸透していた原始宗教だといわれている[21]。岩田慶治は、「アニミズムとは、一般的に精霊信仰と訳され、人間だけでなく、動植物や無生物のすべてがそれ自身の魂(霊魂、精霊、アニマ)を持っているとする人々の信仰を意味する」と述べている[22]。熊野においても、アニミズム的な要素が数多く存在しており、那智の滝に代表されるように、熊野のカミ達の座は、岩、石、樹、森、島、滝、淵、井戸、洞窟と非常に多様である。民俗学者の野本寛一は、自然物をカミの座とすることは、日本全国でもみられるが、その種類の多さ、その質や分布において密であることは、熊野の特徴といえる[23]、と述べている。
―“森”や丘や谷を前にすると動物や他のものだったわたしの前世が現れる−
これはあまりにも有名な映画『ブンミおじさんの森』(2010年)の第一節である。腎臓を病で冒され、余命僅かなブンミは、妻の妹ジェンと甥トンをイサーンの農園に呼び寄せる。そこで、19年前に亡くなった妻フェイが夫の病気を心配して亡霊として訪れたり、数年前に行方不明となった息子ブンソンも猿の精霊となって、ブンミを迎えにやってくる。ブンミは、妻の亡霊、猿の精霊等の「雑多な超越的存在[24]」とともに食卓を囲み、母胎のような「森」において死に向かう。また、前述の『ブリスフリー・ユアーズ』や『トロピカル・マラディ[25]』(2004年)において、「森」は「生(性)/死」や「霊性」を象徴する場所として扱われ、アピチャッポン作品において、重要な位置を占める。
他方、熊野の「森」は、思想史家・山田宗陸が、「クマノは、この列島の住民にとって、根元的な冥界であった。この恐ろしい死の国へいくことは、同時に、いっさいがそこからうまれる原始子宮への胎内がえりでもあった。死と性(正)と霊の伝承が奥深くまじわる[26]」と述べる通り、「生(性)/死」と「霊」が密集する場所である。また熊野の特徴として、森神を祀るものが多く[27]、例えば、田並の矢倉神社[28]は、大樹を中心とした無社殿神社であり、森を神座としている。さらに熊野本宮大社の祭神「家津御子神」は、「木の御子神」といわれており[29]、スサノヲと同一視される樹木神[30]である[31]。このように「森」を象徴としたゾミア的表現は、アピチャッポンと熊野に通底している。
(2)ゾミア的アナーキズム思想
ジェームス・スコットが『ゾミア―脱国家の世界史』で述べる通り、ゾミア世界の歴史を考える上で、大きな障害となるのが「国家」である。まず、アピチャッポンの作品からは、既存国家に囚われないアナーキズム思想が見えてくる。実際に『ブンミおじさんの森』や『ブリスフリー・ユアーズ』ではラオス人やミャンマー人移民労働者などのタイ周辺国のマイノリティに焦点を当ててながら、国家の周縁にいる人々への愛情が示されている。
中央集権国家に対する「しなやかな抵抗[32]」が、アピチャッポンの表現実践の特徴ではないだろうか。それが顕著に現れている例は、イサーン・ナブア村における『プリミティブ・プロジェクト』(2009年〜)ではないだろうか。プリミティブ・プロジェクトにおける短編映像作品『ナブアの亡霊』(2009年)では、イサーンのナブア村の夜の草原で、少年達がサッカーをしている様子が映し出される。燃え盛る炎の塊がボールとして扱われ、その火の玉(魂)は、画面内の白い布に燃え移り、最終的にはその白い布が焼け落ちる。
ナブア村には、アメリカのヴェトナム侵攻が本格化した1960年代後半に、インドシナ空爆のためのアメリカ空軍基地が設置された。1970年代に入ると、反政府勢力である学生達がタイ・ラオス国境に拠点を置き、それに対応する措置として、タイ国軍がイサーンに拠点を置いた。一般市民は暴力から逃れるために森に逃げ込んだ。それらの人々の一部は、共産主義者のレッテルを貼られ、銃撃戦に巻き込まれた経緯がある[33]。明言はされないが、画面上に投射される「火」が、銃火器と虐殺の記憶を炙り出し[34]、国家の暴力性に対して抵抗の意を示しているように感じられる。
また、プリミティブ・プロジェクトの延長線上の作品である『あこがれの光』(2021年)は、タイとラオス国境のメコン川の構図を反転させた写真作品である。メコン川の構図を反転させることにより、抹消された場所の記憶を暗に強調しながら、国家による境界確定と自然に対する開発という暴力性を暗になぞっている。

他方、熊野を起点とした表現でしなやかな抵抗を実践したのが、熊野地域出身の小説家・中上健次(1946年-1992年)である。熊野地域における社会主義活動は、1900年代はじめから活発になる。和歌山県田辺市にある高山寺の住職であった毛利柴庵をはじめとして、大石誠之助や成石平四郎等の社会主義者達は、牟婁新報を通じて初期の社会主義思想を紹介する。特に、大石誠之助は、クロポトキン著『パンの略取』の翻訳を手掛ける等、アナーキズム的な思想に関心を有していた。そんな中、1910年に大逆事件が発生する。天皇暗殺計画に関与したとして、幸徳秋水や大石誠之助等がアーナキストのレッテルを貼られ、証拠が不十分な状態で、24名が死刑判決を受けることになるが、その内の6名が熊野地域出身者であった。この虚構性が明らかになったのは、第二次大戦後である[35]。
戦後を生きた熊野地域出身の中上健次は、被差別部落出身であるが、その生まれ育った周縁の地を「路地」と表現した。中上唯一のルポルタージュ『紀州―木の国・根の国物語』では、消えゆく熊野の「路地」において、消されたアナーキスト達の演説を想像の中で回顧している[36]。また、「路地」という周縁に生きる人達の苦しみと輝きを示した芥川賞受賞作品の「岬」(1976年)をはじめ、「枯木灘」(1977年)や「地の果て 至上の時」(1983年)の三部作は、紀州熊野サーガといわれ、特有の世界感を生み出した。同三部作では、主人公の実父への葛藤と抵抗が表現されている。その実父は、地域の英雄である雑賀孫一の子孫であると称して記念碑を打ち立てる。記念碑を打ち立てることは、国家が行う典型的な行為であるが[37]、まさに、同作における実父は、「路地」を開発、抹消する覇者のような存在であり、国家を象徴していることにほかならない。また、あまり知られていないが、アピチャッポンと同様に、中上健次は16ミリカメラで撮影したフィルム作品も残している。そのフィルムには、奥まった「路地」に住む周縁の人々の日常風景が記録されており[38]、覇者や国家の暴力性に対する静かな抵抗を示しているよう感じる。
(3)ゾミア的口承文化
最後に、アピチャッポンと熊野文化の特徴として、無名の人々による集合的非言語実践がある。『異化されたゾミアの物語―アピチャッポン・ウィーラセタクン「真昼の不思議な物体」を巡って―[39]』で石倉敏明が述べる通り、ゾミア世界の人々は、文書と識字の世界を捨て、文字化されない「語り」によって、戦略的に国家に抵抗してきたのではないだろうか[40]。
この点、アピチャッポン作品では、いわゆる専門職業としての俳優などが起用されないことが多い。前述の中上健次のフィルムと同様に、『真昼の不思議な物体』(2000年)では、「脚本:タイの村人たち」となっているように監督や脚本家の権威性を排除しつつ、イサーンの人々や少数民族へのインタビューを通じて、無名の人々が物語を紡いでいく。
また、前述のプリミティブ・プロジェクトに連なる映像作品『マイナー・ヒストリー」(2021年)は、コロナ渦において、アピチャッポンがイサーン・コンケーンからウボンラチャタニを旅し、イサーンの人々へのインタビューを通じて制作された作品群である。同作品では「ナーガの死」と「メコン川に流れる死体」を起点に物語が展開され、物語の終盤において、反転した巨大な文字の羅列が投影され続け、その「文字による暴力性」が視覚表現で示されている。

他方、熊野信仰の実践は、複数の無名の人々が集まることで生まれてきたものである。熊野地域の独自の祝祭や伝統的表現は、土着の人々やアウトサイダー達が別け隔てなく集まり、それらの知恵が統合したようなものである。また、これらは机上によって生まれてきたものではなく、祭、舞踊やパフォーマンス等の文字化されない「語り」による実践である。
このような祭りは日本全国でも見られるが、その実践における歴史の長さと人々の密集度は特徴的である。例えば、那智大社で行われる火祭では、松明に「火」が灯される。那智の滝の前で点火された真っ赤に燃え盛る松明が、大勢の密集した人々と共に、一二本の扇神輿の周りを繰り返し駆け巡る。これは熊野の土着民と神武軍との間の戦いを再現しているといわれている[41]。また、神倉神社の御燈祭は少なくとも1400年以上続く祝祭である。白装束を纏った男性が、夜の闇の中で、ゴトビキ岩に大いに集い、岩陰で展開される大松明から炎を得た松明を手に、競いながら神倉山を駆け下り、燃え盛る火龍を生み出す。これは、ゴトビキ岩を男根と捉えれば、白装束の男達は精子のようなものであり、他方、火は女性を象徴するといわれている。この集合体による紅白の交わりは、まさに生命の循環を示している[42]。これらの熊野の非言語実践は、原型のない、まさにゾミア的な口承文化ではないだろうか。

4 さいごに ―アピチャッポンの宇宙船―
以上で述べてきた通り、熊野はゾミア世界の一部といってもよいほどに、両世界は深く繋がっているように思う。その繋がりを炙り出すアピチャッポンは、やはり現代のシャーマンだといえるだろう。
ただ、著者が何より興味深いと感じるのは、アピチャッポンが国家の暴力性に対する抵抗を声高らかに主張しているわけではないことである。むしろ、アピチャッポンは、プリミティブ・プロジェクトにおいて、そのナブア村の小さな記憶を炙り出しながらも直接的に批判などはせず、ナブア村の若者と一緒に戯れ、未来について語り合いながら、「宇宙船」を共に制作している[43]。この思想は、ゾミア世界の若手アーティスト達に引き継がれている。
例えば、タイ人映像作家のモンティカ・カムオン(Montika Kham-on、1999年生まれ)とその仲間達は、「サイアミーズ・フューチャリズム」(2021年)において、タイの地方に残る水瓶を宇宙船に見立てて、「仮にバンコクへの中央集権化されていなかったら、イーサンにはどんな未来があったのだろうか」という問いを提示している。イサーン出身のモンティカの母親の物語を起点として、モンティカは眠りに落ちる(本人は眠ることを宇宙船に乗り込む、と表現している)。そこは、過去なのか、未来なのかは解釈が分かれるだろうが、光り輝くイサーンの異人(?)の伝統舞踏とも、コンテンポラリーダンスといえるような身体表現は、宇宙船の搭乗者(鑑賞者)にイサーンの過去と未来について思考を巡らせる機能を果たす。

https://aura-asia-art-project.com/collections/siamese-futurism/#
この作品を見たとき、アピチャッポンが、モンティカに憑依して、著者に未来を見せているのではないかと思ったほどだ。冒頭の「アピチャッポンは、現代のシャーマンではないか?」という筆者の仮説に言葉を足すとすれば、「アピチャッポンは、“未来志向”の現代のシャーマン」なのではないだろうか。アピチャッポンや彼に連なるアーティスト達の表現を踏まえると、熊野を含むゾミア世界から、アピチャッポンのようなシャーマンを生み出す必要性を強く感じずにはいられないのだ。
以 上
[1] 金子遊、『アピチャッポン、全長編映画を語る アピチャッポン・ウィーラセタクン 光と記憶のアーティスト』、フィルムアート社、2016年、14頁
[2] 詳細は、津村文彦『東北タイにおける精霊と呪術師の人類学』、めこん、2015年、67頁-76 頁を参照
[3] 津村文彦『東北タイにおける精霊と呪術師の人類学』、めこん、2015年、55頁-56 頁
[4] 梅原猛、『日本の原郷 熊野』、新潮社、1990年、42頁-44頁
[5] 野本寛一、『熊野山海民民俗考』、人文書院、2010年、7頁
[6] 山口昌男、『筑摩叢書 人類学的思考』、筑摩書房、1990年、同書では、「シャーマンは、心理的に不安定な人間で宗教的生活の召命を受けた人間といえる。隔離、断食、心理的性転換(両性具有)などが訓練の一つである。(中略)彼の魂は体を去り、遠方に旅する—多くの場合霊的世界へ—ことができる。このような条件を通じて、託宣、宗教詩の即興的歌唱、呪的医療の助力の技を帯びることになる」と述べられている。アピチャッポンは、少食で、飲酒もせず、クィアでもあり、両性具有性という観点からも現代のシャーマンといえるのではないか、と感じる。
[7] 中村紀彦、『記憶、儀礼、投影―アピチャッポン作品をつなぐ「アンテナ」、ユリイカ 2022年3月号 特集 アピチャッポン・ウィーラセタクン』、青土社、2022年、71頁
[8] ジェームス・C・スコット、佐藤仁訳、『ゾミア—脱国家の世界史』、みすず書房、2013年、13頁-17頁
[9] 行商の女性、象使いの少年とその家族、劇団員等の老若男女にカメラを向けたドキュメンタリーであり、最後のシーンで登場するサッカーボールのようにリレー形式で、多様な「語り手』が物語を紡いでいく作品である。脚本は「タイの村人たち」と記されているのも、興味深い。
[10] ミャンマーの不法労働者の状況を描いた前半から、後半からは登場人物の3名が非日常の森に入り、自然に還っていく。
[11] ジェームス・C・スコット、佐藤仁訳、『ゾミア—脱国家の世界史』、みすず書房、2013年、19頁
[12] 佐々木高明、『南からの日本文化(上) 新海上の道』、2003年、NHKブックス、58頁-59頁
[13] 岩田慶治、『神と人』
[14] ジェームス・C・スコット、佐藤仁訳、『ゾミア—脱国家の世界史』、みすず書房、2013年、16頁
[15] 五来重『熊野詣―三山信仰と文化』、講談社、2004年
[16] 大林太良『神話の系譜』講談社、1991年、204頁
[17] 鈴木佑記『水のゾミア試論――東南アジアの海民を事例として』2016年、東南アジア研究
[18] 中沢新一『アースダイバー 神社編』、2021年、58頁-61頁
[19] 杉中浩一郎『熊野の民俗と歴史』、1998年、57頁
[20] なお、過去、著者が企画した「水の越境者(ゾーミ)達−メコン地域の現代アート−」展(https://aura-asia-art-project.com/exhibitions/zomi-trans-local-migrants-on-the-water-contemporary-art-from-the-mekong-region/)では、水のゾーミ達が関西に流れ着き、ゾミア世界の最東地を構成したという仮説を提示した。その後、彼らは、関西における弥生的なモノカルチャー的な文化に嫌気をさし、大阪の平地から南に向かい、新しいアジール(避難地)としての熊野の山々に還っていった人々がいるのではないだろうか。
[21] 町田宗鳳、『エロスの国・熊野』、法蔵館、1996年、68頁
[22] 岩田慶治、『アニミズム時代』、法蔵館、2020年、11頁
また、人類学者・奥野克己によれば、「アニミズムの精髄とは、表層的な現実を生きる人間の日常の知だけでつかみ取ることが困難な、言語以前・反省以前の、思議を超えた外部の世界にふれることと、そこへの連絡通路が開かれていて、こちらとあちらで繰り返し何度も何度も行える往還」だと述べている(奥野克己、清水高志、『今日のアニミズム』、以文社、2021年、46頁)。
[23] 野本寛一、『熊野山海民民俗考』、人文書院、2010年、274頁
[24] 金子遊、『東北の発見―アヴァンギャルド/フォークロア アピチャッポン・ウィーラセタクン 光と記憶のアーティスト』、フィルムアート社、2016年、203頁
[25] 物語の前半は、ゲイのカップルの会瀬を描くが、後半からは一転し、森林警備隊員が森を彷徨う姿を描く。映画冒頭「山月記」の引用とクメール人のシャーマンの插話は、シャーマニズムとの関連性を強く示す作品である。
[26] 丸山静、『熊野考』、せりか書房、1989年
[27] 野本寛一、『熊野山海民民俗考』、人文書院、2010年、273頁、274頁
[28] 野本寛一、『熊野山海民民俗考』、人文書院、2010年、236頁-239頁
[29] 紀伊続風土記において「延の熊野坐神社は本国神名帳の家津御子大神にして、家津御子は素戔嗚命の又の御名なり。」と記載されていることからも裏付けられる。
[30] 篠田知和基『世界植物神話』、2016年、八坂書房、24頁
[31] 桑原康宏、『熊野 その表層と深層』、かもがわ出版、2009年、62頁によれば、スサノヲのみならず、熊野に祀られる五十猛神やクマノクスビ等のカミも樹木神、森神であるといわれている。
[32] 徳山拓一、『アピチャッポン・ウィーラセタクン―政治と日常の親密さ』、2017年、Artscape、ウェブサイト(https://artscape.jp/focus/10132997_1635.html)
[33] 四方田犬彦、『アピチャッポンの歴史の顕現 アピチャッポン・ウィーラセタクン亡霊たち』、2016年、東京都写真美術館
[35] 安藤精一編、『図説 和歌山県の歴史』、河出書房新社、1988年、232 頁-236
[36] 中上健次、『紀州―木の国・根の国物語』、角川文庫、1980年、15頁
[37] ジェームス・C・スコット、佐藤仁訳、『ゾミア—脱国家の世界史』、みすず書房、2013年、34頁−36
[38] 金子遊『マクロネシア紀行――「縄文」世界をめぐる旅』、アーツアンドクラフツ、2022年、93頁−103
[39] 石倉敏明、『異化されたゾミアの物語―アピチャッポン・ウィーラセタクン「真昼の不思議な物体」を巡ってー、ユリイカ 2022年3月号 特集 アピチャッポン・ウィーラセタクン』、青土社、2022年、109頁、110
[40] ジェームス・C・スコット、佐藤仁訳、『ゾミア—脱国家の世界史』、みすず書房、2013年、221
[41] 町田宗鳳、『エロスの国・熊野』、法蔵館、1996年、114頁、115頁
[42] 町田宗鳳、『エロスの国・熊野』108頁
[43] 港千尋 、『夜の森で―遊戯と情動のポリティクス アピチャッポン・ウィーラセタクン 光と記憶のアーティスト』、フィルムアート社、2016年、88頁-91頁