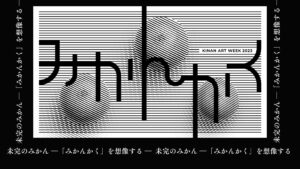みかんコレクティヴ

「みかんマンダラ」展に向けたリサーチまとめ
なぜ人間は、みかんとともに歩んできたのでしょうか。そして、なぜ日本人は、鏡餅の上にみかんを置き、お正月には自宅の玄関に柑橘を飾るのでしょうか。
西洋世界では、みかんは太陽と豊穣の象徴として捉えられてきました。日本でも同様に、橘(みかんの原種)は、太陽神・アマテラスとその系譜を支える機能を果たしてきました。ただ、現代を生きる私達は、太陽神や目に見える果実、資本に頼りすぎてはいないでしょうか。他方、紀南/熊野地域は「根の国」といわれ、樹木神・スサノオを祀る場所でもあります。目に見えない根、菌や土壌、忘れさられた紀南の神々を捉え直すことで、自分たちの「生」を捉え直すことができるのではないでしょうか。
今回の「みかんマンダラ」展は、紀州田辺の大博学者・南方熊楠に敬意を払いながら、密接錯雑としたあらゆる存在を混ぜこぜにしながら、みかんの中に宇宙(マンダラ:サンスクリット語で「丸い」の意味)を見出そうとする試みです。柑橘の香りを感じながら、熊楠のように、自身の「うち」と「そと」に縦横無尽に根を張り巡らせてみようではありませんか。
第1 みかんコレクティヴ:内なるみかん ひらくオレンジ
1 和歌山県/紀南と橘を巡って
和歌山県では、橘本神社が日本における原初の柑橘類である橘やみかんを祀る神社として有名です。常世の国から橘を持ち帰った田道間守神話をはじめとして、橘は、日本書記、古事記の国産神話(イザナギ-イザナミ神話)、弟橘比売命神話等に登場します。
例えば、黄泉の国から戻ったイザナギが禊を行う前の祓詞の中に「橘」という言葉が登場します。そこでイザナギは、禊の後、左目から太陽の神・アマテラスを産み落としますが、橘の木の芽から産まれる果実である橘(みかん)は、それと無関係なのでしょうか。
他方、「根の国」熊野は、アマテラスを祀る伊勢と対置されており、神話世界において追放された側の神であるスサノヲを祀る聖地でもあります。この地で、アマテラス的な側面を持つかもしれないみかんを育てるということはどのようなことを意味するのでしょうか。また、中国やアジアの多くの国では、お正月に親しい人々にみかんを配る風習が残っていますが、これはどのような意味を持つのでしょうか。
2 みかんを再度捉え直してみよう
みかんコレクティヴ(Orange Collective)は、「みかん」に対する解像度を高める実践でもあります。みかんやオレンジ等の柑橘類は、味覚や視覚や嗅覚等を超えて、ロマンや想像力を刺激し、人々をもっとも魅了してきた果実の一つではないでしょうか。
− オレンジは、花と実を同時につけることができ、味覚にも知性にも、訴えるということで、自然の途方も無い豊穣性と、神が人間に惜しみなく与える恩寵を表している。(中略)
また、おそらくもっとも重要なこととして、オレンジの実の丸い形とその色からオレンジの木は、太陽のシンボルとされている。これは、キリスト教の太陽としての存在と関係がある −−
ピエール・ラスロー「柑橘類(シトラス)の文化誌—歴史と人との関わり」より
クラリッサ・ハイマン著「オレンジの歴史」によれば、オレンジは、数百万年前に古代アジア大陸とオーストラリア大陸が分裂する以前に、その境界にある島々で誕生したといわれています。「orange(オレンジ)」の語源は、古代インドの「naranga」、「narangi」に起源があるといわれており、サンスクリット語では「内なる芳香」を意味します。そして、オレンジは、中国南西部、インド南部、ビルマ南部等のヒマラヤ山塊付近の周囲から隔絶された世界において、籠もりながら、その多様性を発展させ、そして、アジアで生まれた柑橘類は、アラビア、ナイル川や中央アジア等を経由して徐々に世界に広がっていきます。特にヨーロッパ世界において、そのエキゾチックな価値が見出され、神や愛や富の象徴として全世界に輸出されていくことになりました。このような文脈を有する柑橘類こそまさに、紀南アートウィークの主題である「籠もること」と「ひらくこと」を体現する果実といえるのではないでしょうか。
また、みかんの木は、枝に白い花々を咲かせ、同時に、黄金色の果実を生み出す独自の特徴を持っています。白い花は「純潔」、黄金色の果実は「多産」の意味を与えます。チーマ・ダ・コネリアーノやガウデンツィオ・フェッラーリの「オレンジの聖母」等の絵画でも、オレンジは、処女でありながら母でもある聖母の象徴として描かれています。また、ボッティチェリ、ダ・ヴィンチ、セザンヌやマティス等の偉大なアーティスト達の絵画表現においては、自然と豊穣の象徴として表現されています。
さらに、マティスにとっては、オレンジは食や象徴を超えた存在であったようです。美術史家のエイドリアン・サールによれば、マティスは、尊敬するアーティストであり、ライバルでもあったピカソに年に一度オレンジを送っていました。なんとピカソは、それを食べないで、「マティスのオレンジ」として眺めるためだけに飾っておいた、という逸話が存在しています。これには一体どのような意味があるのか、一緒に考えてみませんか。
3 みかんコレクティヴとは?
「コレクティヴ(Collective)」とは、集合体、共同体等を意味します。その「コレクティヴ」の定義は多様ですが、私がアジア各地のアーティスト・コレクティヴと関わってきた経験を踏まえると、「コレクティヴ」には、①共通の思想、目的、価値観を有しながら、②異なる技能やバックグラウンドを持った人達が緩やかに集まり、③広く外部と接合しながら集合的実践を行っている、という特徴があるのではないかと考えます。
今回、「コレクティヴ」という言葉をあえて使っていますが、本来であれば、それは言語化されず、お祭り等の伝統行事や神社、寺、教会等を守る無名の人達の集まりの中で自然と実践されてきたようなものなのだと思います。ただ、現代においては、そのようなコミュニティやコモンズが消失しつつあることから、「コレクティヴ」という概念が評価されており、また、本年度ドイツ・カッセルにて開催された現代アートのオリンピックであるドクメンタ15において、インドネシアのアーティスト・コレクティヴ「ルアンルパ」が芸術監督として選任されたことにも象徴されるように、「コレクティヴ」の重要性は増しています。
今回、私達は「アーティスト・コレクティヴ」という社会一般化されつつある概念に、「アート」「アーティスト」等と同等の存在として、「みかん(Orange)」を中核に加えます。
これが意味するところの一つは、脱人間中心主義の観点から、人間ではなく、「みかん」を主体として、その視点の中心に置くことです。人間は、自らの利益の確保のために自然や環境を合理的に管理し過ぎたことにより、生態系や環境を悪化させ続けています。この反省から、世界的に人間以外の生物にも権利主体性を認める動きが主流となっています。芸術の世界においても、人間以外の生物の芸術史(例えば、「パンダの芸術史」や「梅の木の芸術史」等)を思考することが重要となってきています。この観点から、「みかんの芸術史」なるものを思考し、みかんの視座から世界や社会を捉え直す必要性があると考えています。
そして、もう一つは「脱領域化」、ある種の「アート中心主義」への挑戦です。私がアジアのコレクティヴとともに活動する中で感じてきたことは、日本における「アート」の位置付けとは異なる「アート」に対する概念の自由さ、余白の広さでした。アジア地域における「アートのスタンダード」なるものを紀南、そして、日本、世界に紹介していきたいと考えています。
加えて、宮沢賢治は、「農業芸術概論」において、職業芸術家への問題提起とともに、農業を含んだアートなるものの脱領域化の重要性を述べています。私達は、この文脈を踏まえ、文化/アートの創作活動と農業等の一次産業の生産活動は密接に関連しているということ、つまり、「農業=人が自然と共生する創作活動」と捉え、農家は自然との共創を司るアーティストであることを再度確認するため、紀南地域の農家の方々とともに、アーティスト、研究者、民間企業、行政、教育従事者の方々等と一緒に集合的な実践を行います。
以上、「みかんコレクティヴ」では、上記で述べてきたように「みかん」を中心に据え、「みかんと食/農業」、「みかんと自然」、「みかんと神話」、「みかんと贈与」、「みかんと資本主義/グローバリゼーション」等といった視点から、「みかん」を見つめ直していきます。
第2 みかん民主主義 –コレクティヴって何?–
1 みかんは、コレクティヴ?
現代のアート実践では、美術史家クレア・ビショップが述べる「社会的転回(social turn)」が一定の影響力を保持し続けています。社会的転回とは、現代アートの実践において、「美的」価値から「社会的」価値への移行が進んでいる状態を意味します。つまり、作品の態様や新規性より、社会や政治に対する現実的な貢献や影響を重視する潮流のことです。
和歌山県紀南地域のコミュニティも、その他の地域同様、市町村合併、過疎化、インターネット社会の進展等の複合的な要因によって、いわゆる「地縁」に基づく伝統的かつ世襲的な枠組みが「リキッド化(液状化)」しつつあります。その溶解しつつあるコミュニティにおいて、今までとは異なる「新たな関係性」を創出し、再構築するために「芸術」が求められています。増加の一途を辿る地域芸術祭は、そのような背景の証左でしょう。
近年、横浜トリエンナーレやドクメンタ等の重要な芸術祭において、アート・コレクティヴが芸術監督を担っていることからも明らかな通り、芸術を通じて「新しい関係性」を再構築する上で、アート・コレクティヴという集団の存在は重要度を増し続けています。アート・コレクティヴは、持続性や生存可能性の観点から、アーティスト単独ではなく、複数でチームを構成し、その集団的主体性をひとりのアーティストと捉えるような動きです。
–みかんは、ある種の集合体だ -
とある紀南のみかん農家
これは、紀南地域のみかん農家へのフィールドワークを重ねる中で特に印象に残った言葉です。みかんが得た水分や養分は全体で共有されますが、細胞自体は動物のように全体に移転することはありません。例えば、外部から接ぎ木される枝の遺伝子は、クローンとして別個の存在として維持される仕組みとなっています。そのような観点から、異なる存在が同居しながら、統合されているみかんは、まさに集合体(コレクティヴ)のようなものではないでしょうか。また、みかんの果実もある種の集合体のようなものです。みかんを構成する果皮、内果皮、維管束等、その境界は曖昧で、どこからどこまでが全体で、どこからどこまでが部分かは定かではありません。みかんの木、みかんの実も、緩やかなコレクティヴなのではないでしょうか。
2 みかんに “民主主義” はありうるのでしょうか
現在のヒトの社会を見渡すと、SNS等を通じたポピュリズム政治や若者の政治的無関心等、私達は、今まさに民主主義制度の経年劣化に直面しています。もちろん、みかんに民主主義を観念することは馬鹿げた話かもしれないが、ヒトならざるものの視点から思考することは、新たな民主主義を構築する上で重要ではないかと考えています。ただし、みかんに人間の基準(ヒューマン・スケール)を当てはめることは、人間中心主義的ともいえる点には留意が必要です。そのため、みかんの民主主義は、通常の民主主義とは異なる概念として、括弧付きの “民主主義(又は、みかん民主主義)” として表現します。
まず、上記で述べた(集合体としての)みかんは、どのように思考しているのでしょうか。みかんの視座を得るために、ミッシェル・セールの「準-客体」の理論をみかんに適用してみます。「準-客体」の理論とは、受動的な客体(モノ)でありながら、同時に主体として能動的かつ自律的な働きをもって機能する対象の見方です。みかんを「準-客体」として捉え直せば、客体(みかん)は主体(ヒト)に対して従属的な関係から再構築され、むしろ、複数のヒトとみかん、さらにいえば、みかんとみかんとの能動的な相互関係によって、複数のみかんからなる動態を構成することができます。つまり、ブルーノ・ラトゥールがいう「モノの議会」のように、無数の「ヒトならざるもの」に、 “民主主義” といった公益性や社会性を見出せる可能性があります。
そもそも、「民主主義」とは多義的な言葉です。その語源であるギリシャ語の「デモス」とは「人々」のことであり、「クレイトス」とは「権力」を意味します。そして、その重要な要素は、「自由(規則と権力からの分離)」と「平等(資源と権力の公平な分配)」にあり、「自由」と「平等」は、「根」と「枝」の関係のように常に逆向きに作用し、一方が増大すると、他方が減少する関係にあります。この二つの要素が調和するのが民主主義の機能といえます。集合体としてのみかんでは、どのように「自由」と「平等」を調和しているのでしょうか。
紀南のみかん農家にヒアリングを行ったところ、みかんには、人間が刑法等を制定するような、自由を制限するような強権的な仕組みはないようです。例えば、みかんの根は、一部の枝や葉等に水分や養分を行き渡らせないような措置を取ることはできません。逆にいえば、みかんは常に、全体に対して平等な措置を取り続けています。常に平等であるからこそ、幹や枝は常に自由に活動することが可能です。つまり、中枢からの命令により、みかんは幹や枝が伸びることを停止させることはできません。ということは、みかんは、いわゆるヒトの民主主義とは異なり、「平等」と「自由」を完全に保障し、完璧な “民主主義” なるものを構築しているのかもしれません。
デイビット・グレーバーが『民主主義の非西洋起源について』で述べている通り、 ”民主主義” は、古代ギリシャのアテネ等の西洋世界で生み出されたものではなく、ヒトと自然を分割しない先住民族等が生み出してきた生存のための知恵ではないでしょうか。この “民主主義” において、少数者は多数者の意見に従う必要はありません。確かに、自由に伸びすぎたみかんの枝は、重力により折れるなどして自然の摂理に基づいた処理がなされますが、自己の常に自己の存在や判断を正論として主張することが許されています。実は、本来的な “民主主義” とは、みかんの木等の植物や自然が起源の可能性も大いにあるでしょう。今の国民国家によって規律された民主主義は、本来的な “民主主義” ではなく、私達は、みかんの世界から、「自由」と「平等」を再度捉え直すことができるのではないでしょうか。
さらに踏み込むと、ヒトの社会において「自由」と「平等」を調整する上で重要なのが、公共財(コモンズ)です。公共財とは、各個人が共同で消費し、競合せず、いかなる者も排除されずに利用できる施設や物やサービスを意味します。例えば、河川、一般道路や消防、警察等のインフラやいわゆるコモンズ等といえます。ヒトの社会では、公共財は信託される側と信託する側の合意によって、自由と平等を具体的かつ柔軟に調整していますが、みかんの社会では、何がその中枢たる公共財なのでしょうか。
結論を述べると、みかんに中枢はないと考えています。そのため、みかんに公共財はない、もしくは、全ての部分が公共財といえるのかもしれません。もっとも、私は、そのようなみかんにおいても、「根」が公共財といえるような重要な機能を果たしているのではないか、と直感しています。みかんの一大生産地である和歌山県紀南/熊野地域は、「根の堅州国(ねのかたすくに)」といわれる場所です。根の堅州国とは、古事記に記載される地底奥深く、海の彼方など、現世から遠く隔たったところにあると考えられる世界であり、スサノヲ神が宰領する国ともされています。紀南/熊野の住人は、「地中の神」であるスサノヲ神を祀ってきました。上記問いに答えるためのヒントは、視覚で捉えられない、地中で謎に包まれた、みかんの「根」にあるのではないでしょうか。
この点、プラトンは、私達の「頭」、つまり、「理性」を「根」に例えており[7]、アリストテレスも『霊魂論』において、「動物において頭にあたる部分は、植物では根にあたる」と述べています。このように、みかんの知性が想起される場所は「根」なのではないでしょうか。また、哲学者のエマヌエーレ・コッチャが「植物ほど、自分たちを取り巻く世界に密着している生物はいない。(中略)可能な限り世界に密着するために、植物は体積よりも面積を優先するかたちで、身体を発達させている」と述べているように、植物は、動物とは異なり、感覚器官が存在しない代わりに、根を地中に張り巡らせることによって、世界を抱き続けている存在です。みかんは、自身の状態や自身が浸っている環境の状態を獲得し、水分と養分を万遍なく全体に提供しています。そして、みかんは、根を通じて世界を認識しながら、「種の存続」という思想を基礎に、その根、枝、実等、それぞれがまるで意思があるように集合的かつ有機的に行動しながら、全体最適化されています。この全体最適の帰結は「根」によるところが大きいと直感していますが、今後のみかんコレクティヴの活動において、この仮説を更に深めていきます。
3 みかんとヒトの公共財(コモンズ)は何か?
最後に、ヒトの社会に戻ってきましょう。現代アートの実践は、上述の通り、美的価値から社会的価値に重点が移ってきており、その実践において、集合体であるコレクティヴが重要なアクターとなりつつあります。みかんコレクティヴでは、もう一歩踏み込んで、「ヒトの社会」の中に、「みかんの社会」を混ぜ合わせてみます。そこで、ヒトとみかんにおける “民主主義” の土台となる公共財を模索していきたいと思っています。
中空に「根(理性)」を持つヒトと地中に「根(理性)」を持つみかんは、上下逆さまの関係にあるが、これらの間に「重なり合う公共財」を見つけられないでしょうか。きっと「土壌」や「菌」の姿が見えてきそうですが、この「重なり合い」を見出すには、まず「根」のことを深く思考すること、そのために、ヒトが転回し、みかんの根と向かい合うことが重要ではないでしょうか。和歌山県紀南地域がその転回のための要所になっていくことは間違いありません。私達は、スサノヲ神の末裔であり、「根」と向かい続けてきた子孫の集合体(コレクティヴ)であるのですから。
第3 みかん神話 –紀伊半島と橘の関係を思考する–
1 はじめに –明るい闇の国・紀伊半島–
―いまも私には、この紀伊半島そのものが “輝くほど明るい闇にある” という認識がある。
ここは闇の国家である。日本国の裏に、名づけられていない闇の国として紀伊半島がある―
――中上健次『紀州 木の国・根の国物語』
「紀州 木の国・根の国物語」は、紀南/熊野が生んだ偉大なるアーティスト・中上健次(1964-1992)が残した唯一の探訪記です。「根の国」である紀南や熊野地域は、スサノヲが統治する「木」と「根」によって混沌とした異界ともいわれ、差別・追放された敗者達を受け入れ続けた場所です。そのような異郷の地にも関わらず、中上健次はなぜ「輝くほど明るい」という言葉を使ったのでしょうか。これを考える上で、みかんや橘といった柑橘が一つのヒントを与えてくれます。
2 植物と神話 –柑橘と太陽–
神話とは何でしょうか。ルーマニアの宗教学者ミルチャ・エリアーデ(Mircea Eliade,1907-1986)は『神話と現実』において、「神話とは神聖な歴史を物語る」ものであり、「常に『創造』の説明であって、あるものがいかに作られたか、存在し始めたかを語る」ものであると述べています。
その神話の中でも、植物や柑橘に関係する神話は世界に数多く存在しています。杉、欅、リンゴ、桜、桃、蓮、バナナ等、その種類は非常にたくさんあります。それは、人も自然も、同様に、それぞれの種を残し、殖やしたいという願望を持っているからでしょう。そして、各地域の風土に合った植物が、人々の理解を促進するための象徴やメディアとして、神話の中で活用されています。例えば、インドネシアやニューギニア等の南洋における「バナナ神話」や、日向神話におけるニニギとコノハナサクヤヒメの「木の花神話」が挙げられます。これらにおいては、風土の差異に基づいて、「バナナ」と「美しい花」といった異なった植物が題材とされていますが、ともに、人間の死の起源について説明がなされている点は同様です。
また、柑橘類でいえば、ギリシャ神話におけるアテランテの愛の神話、ボッティチェリの「春(1478年頃)」や「ヴィーナスの誕生(1485年頃)」、セザンヌの「林檎とオレンジの静物(1899年頃)」等の偉大な西洋画家達の絵画表現において、柑橘類は、自然と豊穣の象徴として表現されてきました。そして、何より柑橘類は、その丸い形とその色から、太陽のシンボルとされてきました。では、柑橘類は、日本においても同様に、豊穣や太陽の象徴として捉えられてきたのでしょうか。日本神話における太陽と橘の関係について、考えてみたいと思います。
3 日本神話と橘
(1)記紀神話 -南方系の植物神・スサノヲと北方系の太陽神・アマテラス-
古事記と日本書紀(以下、「記紀神話」)は、①中国南部から東南アジア(南方系)、②朝鮮半島と内陸アジア(北方系)等といった様々な系統の神話が多層的かつ多元的に集まって構成されているといわれ、記紀神話の天岩戸神話では、アマテラス(生、秩序、太陽の神)とスサノヲ(死、破壊、海原、根の神)の対立構造が描かれています。
この内、スサノヲは、東南アジアの日食月食起源神話における乱暴な末弟「ラーフ」と特徴が類似しています。また、東南アジアでは、神や精霊が樹木に宿るという信仰が多く存在していますが、紀南/熊野の土着神であるスサノヲも南方的な植物神といわれています。さらに、スサノヲが高天原で乱暴狼藉を働き、アマテラスの畑の畦を壊したり、糞を撒き散らしたりしたのは、スサノヲなりの農業(焼畑)だったのではないかともいわれ、スサノヲに斬り殺されてしまったオオゲツヒメの死体からは、ヒエ、アワ、大豆等の雑穀栽培型の焼畑作物が多く生まれています。このように、スサノヲには南方系及び縄文的農耕の性格が色濃く反映されています。
他方、アマテラスは、世界に秩序と光をもたらす太陽神である。アマテラス系の天孫降臨神話(天皇系の先祖が高天原から降りてくる物語)は、古墳時代に、華北からユーラシア大陸における大動乱の影響を受けて、朝鮮半島から、支配者文化の一環として入ってきたものだといわれており、その動乱の最中、日本の「体制変革」において、新しい思想を導入するための建国神話として政治的に活用されてきました。その意味で、太陽は、外部からの支配者が王権を樹立する際に、特定の土地や家系に縛られずに、統一的なイデオロギーを構築するのに強力なツールだったといえます。上記ミルチャ・エリアーデの神話の定義に照らせば、天孫降臨神話とそれに連なる神武東征神話は、中央の支配者集団の中で伝承される“神聖な”国家の物語なのでしょう。
(2)田道間守、弟橘比売命、イザナミの祓詞 -橘を巡る神話-
そのような文脈において、日本における原初の柑橘類である「橘」は、どのように機能するのでしょうか。記紀神話には「橘」という言葉が多く登場しますが、これは太陽や秩序の象徴としての柑橘と何らかの関連があるでしょうか。
まず、橘に関連するものとして、病床に伏せる垂仁天皇のために、常世の国から橘を持ち帰ったという田道間守神話が有名です。田道間守は、和歌山県海南にある橘本神社において主祭神として祀られています。橘は、ここでは「非時香果」と呼ばれ、その黄金色に輝く丸い実は、不老不死の力を持っているといわれています。ここにおける「ときじく(非時)」とは、時間に左右されないことであり、「かく(香)」は、「香りのよい」「輝く」という意味で使われています。光輝く橘は、常世から現れ、永遠に周期運行する太陽のような長寿と幸運をもたらすと思われていたのではないでしょうか。現代でいえば、橘は、光り輝く金や貨幣のように人々を魅了するものだったのでしょう。
また、記紀神話の中盤で大活躍するヤマトタケルの妻である弟“橘”比売命の名前に「橘」が登場しています。弟橘比売命は、走水の海(浦賀)でヤマトタケルの身代わりとして犠牲となりますが、その結果、暴風雨を鎮め、ヤマトタケルの東征を前進させる役割を担っています。ヤマトタケルは、玉浦(現在の九十九里浜)で、名に因んで橘の木を妻の墓標とします。これは、巫女が荒ぶる海原を制御する人身御供の信仰を活用し、橘を表象する巫女が、アマテラス的な女神信仰と再生力を象徴する機能を担いながら、スサノヲ的な荒ぶる力を相対的に制御し、低下させる効果を生じさせています。
最後に、イザナミから追われ、黄泉の国と海原の境界に戻ったイザナギが禊(穢れを取り除くための水浴行為)を行う場面に戻ります。イザナギが、その左目からアマテラスを生み出す場所は、「筑紫の日向の橘の小戸の阿波岐原」と言われていますが、この祓詞の中にも「橘」という言葉が登場します。
まず、ここにおける「日向」は現在の宮崎県という特定の場所を示すともいわれていますが、「朝日直射す国」、つまり「日光があたる場所」の総称ではないでしょうか。「日向」とは、まさにアマテラスが象徴する太陽の在り処であり、そこに太陽の象徴と思わしき「橘の木」があったとしても違和感はないでしょう。
また、「橘」の「たつ」には、「真っ直ぐ直立している」、「自然界の作用が目立って現れる」という「立つ」という意味に加えて、「繋がっているものを切り離す」という「断つ」の二重の意味が含まれているのではないでしょうか。「橘」は、天高原と黄泉国のあいだに存在する地上に、毅然と直立する神聖な樹木として存在していたのではないでしょうか。筆者は、三貴神の登場シーンにおいて、アマテラスの存在感が、橘の存在も相まって、極めて強調されるイメージを持ち続けています。
ちなみに、現代においても、その柑橘類の果実は、正月の鏡餅の上に飾られたり、玄関に設置されたりといった一種の魔除け(破壊や不幸を切り離す)の機能を果たしています。すなわち、柑橘は、「秩序-正」を維持し、「混沌-負」を切り離そうとするアマテラス的な思想性をもった象徴的な植物なのではないでしょうか。
4 闇の国家の視座から
さて、最初の問いに戻りましょう。中上健次は、なぜ紀伊半島を「輝くほど明るい闇の国家」と表現したのでしょうか。筆者は、中上健次のこの言葉に一種の皮肉と紀伊半島への誇りを感じられずにはいられません。上述のとおり、みかんの神話を紐解いていくと、その裏側には、アマテラスとその子孫の支配論理が浮かび上がってきます。すなわち、絶対的な光と秩序の正の原理が、闇と混沌の負の原理を打ち倒すという構図です。
紀伊半島は、スサノヲが統治する「根の国」を起源とするにもかかわらず、日本で最も多くの柑橘類が生産地されています。即ち、支配者によって統治された「根の国」において、太陽の化身である柑橘が大量に生産されている姿(特に、中上健次が生きた1960年代〜1970年代終わりにかけて、生産量が急拡大している)は、まさに太陽の烙印のように感じたのではないでしょうか。中上健次は、そんな状況に皮肉を込めて、「輝くほど明るい闇の国家」という表現を用いたのではないでしょうか。
もう一点、中上健次は、「輝き」や「明るさ」に惑わされ続けている人々を皮肉っているのではないでしょうか。「Capitalism(資本主義)」の語源は、「Caput」に由来します。「Caput」とは、「先端部分」や「頭」を意味し、植物においては雌しべの先端、つまり「果実」を意味します。果実、ひいては貨幣の増殖ばかりを目指す現代社会に、「闇の国家(木の世界/根の世界)」の重要性を説きたかったのではないでしょうか。先端や果実を志向するのではなく、木や根自体を思考することの重要性が増している現代において、中上健次の言葉が突き刺さります。これは熊楠の根源的なものを志向する世界感とも重なり合うようにも思います。現代において「資本」として捉えられていない「根」、「樹木」や「土地の神々」等を<資本>として捉え直すことが必要な時代になってきているように思います。
最後に、その「(果実型)資本主義」が蔓延する時代において、中上健次は、「正/負」、「アマテラス/スサノヲ」、「果実/根(木)」は、不可分一体の関係にあり、根や闇等といった負の概念が重要であること示したかったのではないでしょうか。だからこそ、紀伊半島を「明るい闇の国家」というパラドックス的な表現とした可能性があります。 この点、アメリカの歴史学者ジェームズ・スコット(James C. Scott)は、この正と負の不可分離性を「闇の双生児」という言葉で表現しています。つまり、「国家民/非国家民」、「農耕民/狩猟採集民」、「文明人/野蛮人」は、記号としても、実態としても双生児であると主張しています。国家や文明人が消滅すれば、非国家や野蛮人が消滅する(その反対もしかりである)、という歴史的事実があります。そして、スコットは、皮肉的な意味合いで「野蛮人」という言葉を使いながら、「国家」や「文明」の世界を生きる私達よりも、「野蛮人」が、世界でもっとも長く、より自由で平等な黄金時代を謳歌してきた、という衝撃の事実を記しています。そう考えると、中上健次の真の意図は、単純に言葉そのままに「闇の国は、誇らしいほど輝いている(国家や誰かに飼い慣らされずとも、自由で、平等で生存可能性が高い)」ということを伝えたかったのもしれません。
紀南アートウィーク実行委員長
藪本 雄登