みかんコレクティヴ
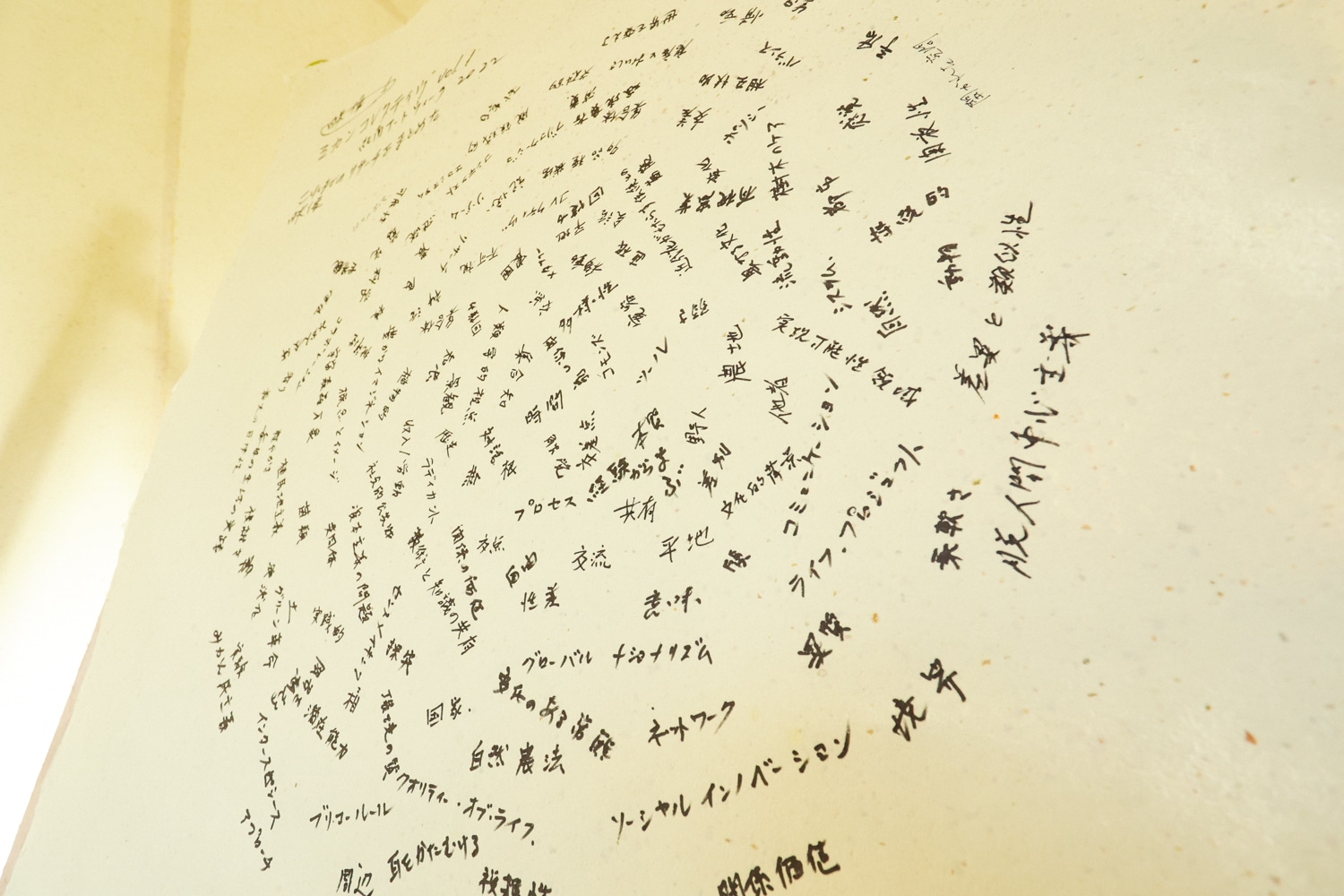
「コモンズ農園」の歴史的文脈を語る(後編)
住友:「アルテ・アビタビーレ」の話で思い出されるのは、廣瀬さんが「コモンズ農園」と同じように土地と関わるプロジェクトを、じつは1996年に札幌で《生きられた土地》というタイトルで実施していたことです。これはバブル景気がはじけた後、空き地となって放置されていた土地に簡易な舞台を設置し、パフォーマンスやワークショップをおこなうものでした。カフェもあり、話し合いの場も持たれたようですし、テントが並び、そこで寝泊まりもできました。また、同時に開催されたギャラリーの展示は匂いや色で来場者の感覚を刺激するものだったようです。佐賀町エキジビットスペースで同年発表した《マーレ・ロッソ(ノット・ホール)/プロジェクトA.P.O.》も、大きな絨毯のうえで観客が思い思いに過ごすための場所をつくり、屋上で寝泊まりする活動を行なったという点では共通しています。
廣瀬智央《マーレ・ロッソ(ノット・ホール)/プロジェクトA.P.O.》1998年、「プロジェクトA.P.O.」展
(佐賀町エキジビットスペース、1998年)の展示風景、写真:Tartaruga、提供:佐賀町エキジビットスペース
物質ではなく実践を志向する特徴は、金井さんが指摘されるようにアマルフィのアツィオーニ・ポーヴェレにつながっていきますが、アルテ・ポーヴェラの作家は政治運動に積極的に関与しているとはいえないようですね。しかし、オブジェではなく行動を重視することが批評家たちとの間で模索され、鑑賞者の知覚を刺激し、共同体に働きかけるような行動が目指されていたように思います。今回の廣瀬さんの展示では、地域の農家が共同利用している倉庫を使って、蜜柑の匂いや色を堪能するものが置かれ、さらに同じ場所で《みかんの苗木の旅》が開始し、新しい農園をつくる提案が示されました。イタリアの先達たちや佐賀町ではもっと緩やかな行為が志向されていたのに比べると、農業や社会が直面している課題に対して直接的な行動をうながすような特徴があるように思えます。
ドクメンタ13はアルテ・ポーヴェラの作品を多く所蔵するカステロ・ディ・リヴォリの館長キャロリン・クリストフ・バカルギエフによって企画され、たしかにボエッティの作品が象徴的な役割を果たしていましたね。並べられた作品の関係性のなかに美術史を読み解く楽しさにあふれた展覧会として素晴らしいものでした。しかし、そのことと金井さんが言及された反グローバリゼーション運動のテント村は興味深い対比を見せているように思えます。つまり、一部の者たちに共有された美術の豊かさ(リッカ)に対して、行動によって直接的に不平等の是正を訴えた人たちがいたということではないでしょうか。
その点で、今回のドクメンタ15はまさに反グローバリゼーション運動をはじめ、周縁化され不安定な状況にある人たちの連帯を叫ぶ声が展示室の内に充満しているような企画でした。フレデリチアヌム美術館の外側と内側が逆転してしまったような現象ですね。ジェイソン・ファラゴのように外側に出されてしまったと感じた人も多かったでしょう。彼は、アートではなく、友人たち(と敵)だけの展覧会と批判し、それを仲間うちの内向き姿勢とみなし、ユダヤ民族差別が発生したことと結びつけた記事をニューヨークタイムズに寄稿しました。しかし、ファラゴが言うようにこのドクメンタが公衆を無視して自己満足していた、と見るのは私の実感とは違いました。むしろ逆です。
今回のドクメンタはウェブサイトに「easy read」という通信容量を抑えて平易な言葉で伝えるページがあったり、子供向けにコンセプトを伝える展示もありました。美術館のなかには託児所があって実際にとても多くの人に利用されていましたし、植物を育てるガーデニングやストリートカルチャーの要素も多く、美術愛好家だけでなく幅広い市民に親しみやすい展覧会として受け入れられていたと感じます。そして、作品がユダヤ民族差別と批判されたタリン・パディが占有していた展示室では、ドイツ語通訳を入れたアーティストのギャラリーツアーが行われていて、熱心なドイツ人来場者たちが終了時に拍手を送っている光景も目にしました。しかし、美術の知識によって作品と向き合う気満々だった来場者は外側に押し出されたような思いをしたかもしれません。
しかし、美術の歴史と関係がないとも思いませんでした。とくに、私は表現を支えたメディアに注目するべきだと感じました。絵画や彫刻は少なく、映像や写真、そしてテキストや音が圧倒的に多かったんですね。映像のなかで、アーカイヴ資料のなかで、あるいはDIY的な手仕事感覚あふれる造作のなかで、声とテキストを通して印象的なフレーズにあちこちで出会いました。それらは、アカデミックな教育を受けていなくても、技術的に洗練されていなくても、高価な材料や機材を使わなくても作れる、という共通点があります。これはリパードが「廉価で、一時的で、非抑圧的なコンセプチュアルな媒体」と書いたメディアの特性と重なり合うように思えます。
そのことにもっと意識を向けてみると、ドクメンタ15にはグローバルサウスといわれる非欧米圏のアーティストが数多く参加していたわけですが、1999年にクイーンズ美術館が企画した「グローバル・コンセプチュアリズム」展に再注目してみる必要があるかもしれません。これはリパードのアルゼンチン体験、及び「ナンバーショウ」の後半に女性アーティストを多く含めたことを念頭におくと、ニューヨークで起きた芸術運動を普遍化させることなく、コンセプチュアルアートの可能性を地域の社会や文化と関わるものと広義にとらえた企画として非常に重要な試みだったと思います。ちなみに、リパードはその後、ニューヨークを離れてニューメキシコに移り住み、先住民族の文化、エネルギーや環境の問題、自然と人間や生き物との関わり合いなどに強い関心を向け、その多様な存在を認めるための市民運動においてアートが果たしている役割をめぐる著作を書き続けています。なので、彼女が辿った道のりはドクメンタ15へとつながっていたのではないかと私は想像してしまうのです。もちろん、ドクメンタ15がコンセプチュアルアートの嫡子であったとは思っていません。ただ、リパードを補助線にして歴史と地域を斜めに横断するような批評の可能性を感じているということです。
さて、ここで紀南に話題を戻すと、今回のドクメンタで声を上げていたのは資本主義やグローバリゼーションによって不安定な立場に追いやられているマイノリティ、あるいは自然環境や安全を破壊され危機に晒されている人々や生物たちです。その視点に立てば、二次産業や三次産業の力が一次産業を大きく凌駕しつつある点が問題を引き起こしているといえます。農業、林業、漁業などの営みは私たちのもっとも基本的な生活を支えるものですが、古い村落共同体の因習と身体労働の負担がおもな原因で担い手を減らしつつあります。これらは性的マイノリティ、あるいは障害を持つ人々を虐げ、安い労働力の搾取を生んできました。いっぽうで、先住民の知恵をはじめ、自然と深く関わり、人間中心主義を再考する機会を多く与えてくれ、私たちがこれからどのような社会を築くべきかを考えるうえで重要な活動です。「グローバル・コンセプチュアリズム」展の図録で、私はタイのアピナン・ポーシャナンダがコンセプチュアル・アートは癒しをもたらしたと書いていたことが気になっていました。トートロジカルな、還元主義的なコンセプチュアル・アートに癒しのような効果があると思えないからです。しかし、彼の文章は植民地支配の影響を受けた美術アカデミズムの普遍主義に違和感を抱いていたアジアの芸術家たちが、コンセプチュアル・アートを経由することで固有の文化や同時代とアートの接点を見出すきっかけを切り拓いたことを指摘していて、それは今のアジアの美術を理解するうえでかなり重要な気がします。そして、それは植民地支配とその後の冷戦体制によって抑圧されてきた文化の多様性を回復し、またさまざまな差別に抵抗するための市民運動と結びついてきたんだと思います。そのなかには、今回のドクメンタに参加した団体のように農業や伝統文化に目を向ける芸術家が多くいました。廉価で誰でも手に取ることができるメディアがこうした活動をおこなう芸術家たちに表現する可能性を与えたんでしょうね。
また、文芸や音楽が重要な技芸とされてきた西洋では言葉や数字を扱う抽象的な能力を重視し、肉体労働を下に見るヒエラルキーがあったように思います。例えばキャロリン・コースマイヤーなどはそこに手芸や工芸を担う女性の役割を低く見てきた歴史を重ね合わせています。それに対して、身体の役割を回復させることもアツィオーニ・ポーヴェレやリパードの批評活動、そして農業と芸術の実践が目指しているものかもしれません。
廣瀬智央《みかんコレクティブ》2022年、展示風景(一部)、写真:下田学(coamu creative)
それから、金井さんがボエッティの《双子》という作品や彼の署名を通して、彼の脱中心、脱領域的傾向を指摘していたのも大変興味深い点ですね。これを、「私」の分裂とみなし、彼がワンホテルなどを経営していく活動とつなげていけるのかどうか。たしかに、現代の芸術家がプロジェクトや事業を起こしていくのとは異なると思いますが、脱中心化を志向していたとみてもよさそうに思えます。
1960年代にはアラン・カプローが「環境(エンヴァイロメント)」という言葉を使い始め、作品が自己完結しているのではなく、周辺の環境と連続している点を強調し、偶然性などを考慮し、表現主体がコントロールしない方法が提唱されました。アルテ・アビタービレと同時代の出来事ですよね。個人、作者、作品の自律性を強く求めてきた近代芸術の理念に対する疑問が差し込まれるようになったともいえます。1980年代以降のグローバル化を振り返ると、自由で自律的に振る舞う個人というのは競争を煽る新自由主義経済と相性が良く、それは弱い立場の人たちをますます衰弱させてきたと思います。ドクメンタ15が「友人」という呼び方で連帯を呼びかけたのも、そうした背景があるからです。そして、差別などで傷ついた人たちは個人ではなく複数の人たちと関わり合い、仲間を見つけ出すことで癒されていきます。いっぽうでイタリアは1970年代に激しいイデオロギー対立の「鉛の時代」に入ります。そうした背景をもとに考えると、ボエッティがなぜカブールにホテルを作ったのかも理解できるような気がしてきます。1960年代のアファーマティブ運動はしばしば激しい暴力を伴いましたが、それから50年経ったカッセルではマイノリティの権利獲得のための活動をおこなう人々が連帯を呼びかけ、視覚表現だけでなく、言葉や音も使った主張が繰り広げられました。脱中心化という作用を通して、時代の変化をみていくこともできそうです。
金井さんは、アルテ・ポーヴェラのアーティストたちと1968年前後の社会を詳しく調べられてきました。そこから50年以上が過ぎた現在、同時代の差し迫った社会問題と作品制作や実践のあいだにはどのような関係が生じていると考えられていますか。
金井:ドクメンタ15について、そして表現メディアの問題について、とても興味深く読ませていただきました。なるほどリパードを、とくにアルゼンチン渡航以後の彼女の活動を念頭に、グローバル・コンセプチュアリズム、さらにはドクメンタ15を捉えることは非常に重要ですね。今年カッセルに行かなかったことがますます悔やまれてきました。一連の報道の量と内容に気が乗らず、今回はパス、むしろ評判芳しからぬヴェネツィア・ビエンナーレへ、と、ちょっとひねくれて動いたのですが、やはり失敗でした。ヴェネツィアでのんびりしすぎました。
さて、社会問題と作品制作の関係について。かつての韜晦な、あるいは抽象的なコンセプチュアル・アートに代わって、社会ないしコミュニティとの関係を重視する芸術実践が大きく注目を集めていることは周知のとおりです。そのなかで、タイムスペシフィックというコンセプトも聞かれるようになってきました。かつてのサイトスペシフィック・アートが、えてして男性芸術家によるランドアートを範例として語られてきたことに真っ向から対立するような、時宜と機略の実践/戦術です。インパクトと実効性、波及力が鍵で、つまりわかりやすい(と言ってよい)。政治的手段ともなりうる。近代的な芸術観に引導を渡すようで、じつに今日的ですが、一方で私がそれに近い例として連想するのは、じつは17世紀バロックの美術です。たとえばカラヴァッジョの直接性です。その様式は聖画像による教化を重視した16世紀のカトリック改革(controriforma)に起源をもつもので、フランク・ステラが語ったように、まさに鑑賞者に作用する絵画となっている。観る者を瞬時に巻き込むリアリズムです。もちろん《エマオの食事》と、タニア・ブルゲラがテイト・ギャラリー内に騎馬警官を引き入れたことが、同質にリアルだというわけではないですが、少なくとも両者ともに観者の参加が鍵であり、その経験の記述も困難ではない。その意味で、すべての人に開かれている。美的切り離しをもって成り立つ近代美学や西欧近代のアヴァンギャルドのルールの外部で、新旧のラテン世界が符丁を合わせているようで、私にとっては非常に興味深いケースです。
ところで現代美術における時間の扱い方ですが、タイムスペシフィックというかたちで世事を織り込まずに、逆にもっと開く方法もありますね。コンセプチュアリズム勢としては、河原温や松澤宥の時間の扱い方がすぐに思い浮かびますが、アルテ・ポーヴェラでいうと、やはりジュゼッペ・ペノーネでしょうか。彼は1968年以来、木の成長や、大理石の生成、河川による岩石の侵食など、人間以外の生物や無生物の時間の層にふれる彫刻作品を次々と発表してきました。デディ=ユベルマンのペノーネ論に拠るならば、「所産的自然」ではなく「能産的自然」への関心です。エージェントとしての生物・無生物とも言えるでしょう。また、ペノーネ自身こう言っています。「彫刻をとおしてつくっているのは、文化的産物ではない何かだ」。
イタリア語で彫刻はsculturaです。私の好きな言葉遊びなのですが、sculturaはs-culturaに通ずる。接頭辞sには分離・除外・逆のニュアンスがありますから、つまり彫刻とは文化culturaの外。ペノーネの言うとおりともいえます。もっともペノーネが一途に文化の外部に向かっているかといえば、そうでもなく、たとえば《流動する彫刻の庭》(2003-07)のような近年の庭園での活動はculturaとsculturaのあいだを見据えた長期スパンの試みとなっています。あるいは遡って70年代の《ジャガイモ》には、身体を象る初期ペノーネの関心に加え、ほぼ農業=土文化agriculturaのプロセスがある。ひたすらジャガイモを栽培するわけですから。いずれにせよペノーネがより大きな時間の流れや循環に棹さす制作を半世紀続けてきて、それがある種の謎を醸しつつ、現在もなお、いや、今あらためて同時代のエコロジカルな関心と接続しえていることは、ひとつの驚きです。それは時宜と機略の実践/戦術とは真逆の緩慢さで成り立つものですが、しかし、そこにもまた別のタイムスペシフィシティがあるはずです。廣瀬さんの紀南での活動もこのあたりにつながってくるのでは、と思います。廣瀬さんにも伺ってみたいところです。
住友:美的切り離しによって成立する近代美学に対して、時宜と機略の戦術が駆使されてきた歴史はたしかにとても興味深いものですね。布教や改革、そして政治実践のために、経験の強さを重視するのはいつの時代でも見られる手法といえます。それと同時に、タイムスペシフィックとは対極にあるようにみえる無生物の時間に触れる作品について言及いただいたのもとても示唆的でした。金井さんは、ペノーネの活動を通してこの二つは対立的なのではなく、大きな時間の流れに棹さすようにみえてそれがエコロジカルな関心のように現代のタイムスペシフィシティと通じ合うものがあると指摘されています。この二つを対立させてしまうと、長い時間をかけた変化は個人の限られた時間と無縁のものとして感得されてしまう危険があります。だからこそ、その間を埋めて連続性を感じとらせる試みは重要ですし、芸術にその役割が求められると期待を込めて考えたくなります。あえて「文化的所産ではない」とペノーネが述べたのは、人間の営みである文化を超えるものとしてとらえるためだったのでしょうか。
この時間の捉え方は廣瀬さんの作品でも随所に見出せます。各種の豆や丸められた地図、そして鉱物がアクリル樹脂に閉じ込められ、宇宙の星々のように見える《ビーンズ・コスモス》や長年継続されている空の写真シリーズなど、移ろいやすいものとずっと続くものの双方が凝縮されているような作品です。平面作品も含めて、彼の作品には彫刻的な物質性を強く感じるものが多く、s-culturaが「文化の外」という意味も持ち得るという金井さんの指摘によって、それらの作品に関する解釈を広げることもできそうです。
廣瀬智央《ビーンズ・コスモス》、アクリル樹脂、マメ科植物、プラスチック、金、地図、ビー玉、など、
2015年、写真:内田芳夫、提供:小山登美夫ギャラリー
また、地球上の生物や食糧生産者こそ、大きな時間の流れ、あるいは循環的な時間を感じ取っているものたちです。その経験と知恵は、近頃メディアでよく聞くSDGs(持続可能な開発目標)やCOP(気候変動枠組条約締約国会議)が注目される以前から積み重ねられてきています。そして、大企業や国際会議中心の時宜的な実践をめぐっては、この枠組みを主導する先進諸国への不信感が拭えきれない人々が大勢いるのも事実です。グローバルサウスからは、「文化」を規定づけてきたのは誰なのか、その外側に置かれてきたものは何なのか、と問いかける声も聞こえてきます。ドクメンタという西洋の歴史的文脈に大きく規定づけられてきたアートの主戦場でその声が響き渡ったのには大きな意義があったはずです。はたして、それは大きな時間の流れのなかでどのような転回を示すものになるのか。同時に、一粒の豆を愛でたり、ピアノの一音に心を動かされたり、少し現実から身を引いて静かな時と場所を確保する芸術の役割とどのような関係にあるのか。
金井さんには、およそ二ヶ月かけて、アルテ・ポーヴェラとその後の展開を、紀南における廣瀬さんの「コモンズ農園」提案と結びつける話にお付き合いいただきました。そのなかで、ボエッティの「脱中心化」、ペノーネの「文化の外」という概念を教えていただき、今後の活動のヒントにさせていただきたいと思いました。どうも、ありがとうございました。
金井直(信州大学教授)
1968年福岡県生まれ。豊田市美術館学芸員(2000~07年)を経て、2007年より信州大学人文学部に勤務。主なキュレーションに「アルテ・ポーヴェラ」(豊田市美術館、2005)、Vanishing Points(ニューデリー国立近代美術館、2007)、「あいちトリエンナーレ2016」(共同キュレーション、愛知県美術館他、2016)、著書に『像をうつす 複製技術時代の彫刻と写真』(赤々舎、2022)、共著に『彫刻の解剖学』(ありな書房、2010)、共訳に『Art since 1900』(東京書籍、2019)などがある。
住友文彦(東京藝術大学教授)
1971年生まれ。ICC/NTTインターコミュニケーションセンター、東京都現代美術館学芸員などを経て、2013年から2021年までアーツ前橋において館長を務め、コミュニティと関わる各種プログラムを実施。「境界 高山明/小泉明郎」(銀座メゾンエルメスフォーラム、2015年)、「あいちトリエンナーレ2013」、「メディアシティソウル2010」(ソウル市美術館ほか)、「川俣正[通路]」(東京都現代美術館、2008)などを企画。



